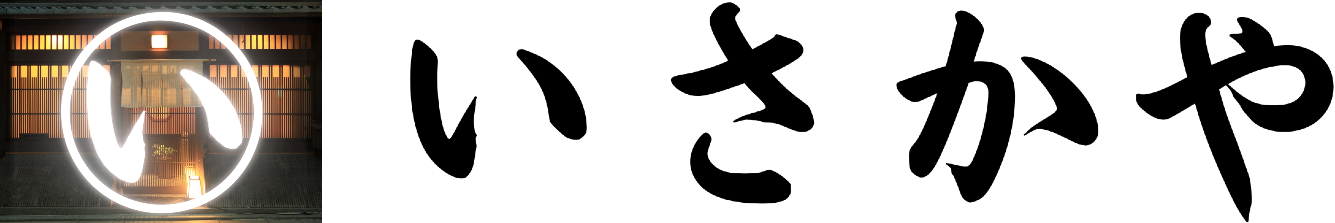※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
夕暮れ時の月島。西仲通り商店街の喧騒から一本路地を入ると、そこはまるで時間が止まったかのような静けさだった。細い路地の奥に、古びた木造二階建ての一軒の居酒屋が赤提灯を灯している。「おばち」。40年以上この場所で営業を続ける老舗だ。
私、いさかやは居酒屋をめぐり歩くライターである。「月島の秘境居酒屋」という企画で今夜はこの店に足を運んだ。
店の前に立つと、扉の向こうから漂ってくるのは煮込みの香りと、かすかな笑い声。暖簾をくぐると、狭い店内に詰め込まれたカウンターとテーブル席がある。壁には魚拓や古びた写真が所狭しと飾られている。
「いらっしゃい」
店主の渋井さんは70代とは思えない力強い声で迎えてくれた。禿げ上がった頭に白いタオルを巻き、手際よく鉄板を拭いている姿は、まるで職人のようだ。このあたりはもんじゃ焼きで有名だが、「おばち」は違う。もんじゃも出すが、本当の売りは牛モツ煮込みだという。
カウンターに座ると、右隣ではすでに一人の中年男性が熱燗を呑みながら、煮込みをつついていた。目の前の棚には日本酒の瓶が並び、古い木の天井からは年季の入った照明が温かな光を落としている。
「何にします?」渋井さんが尋ねる。 「とりあえず生ビールと、おすすめをお願いします」 「わかった。今日は牛モツ煮込みがいいよ。朝から仕込んでる」
ビールが運ばれてきた。一口啜ると、ほどよい苦みが喉を通り抜けていく。その後に出てきた牛モツ煮込みは、深い茶色の汁に様々な部位のモツが浮かんだ、見るからに染み込んだ一品だった。
「いただきます」
一口食べると、口の中に甘みと旨みが広がる。やわらかいモツもあれば、コリコリとした食感のモツもある。濃厚なのに、不思議と飽きない味わい。
「どう?」 「美味しいです」 私の素直な感想に、渋井さんは満足そうに頷いた。
「この味、何十年も変えてないんだ。うちのモツ煮は戦後の食糧難の時代から始まってね。当時は高級な肉なんて食べられなかったから、モツみたいな内臓を美味しく食べる知恵が生まれたんだよ」
渋井さんは語り始めた。月島は明治時代の埋め立てで生まれた土地で、もともとは漁師や工場労働者の街だったという。このあたりの居酒屋文化も、そうした働く人々の憩いの場として発展してきたのだ。
「今じゃタワーマンションも建って、客層も変わってきたけどね」 渋井さんはそう言いながら、店の奥のテーブル席にいる若いカップルに目をやった。
「でもね、味だけは変えちゃいけない。それがうちの矜持なんだよ」
話を聞きながら、私は店内を見回した。カウンター席には地元らしき常連客が数人。テーブル席には観光客や若いサラリーマンのグループ。そして窓際の小さなテーブルには、一人の老紳士が座っていた。
白髪交じりの髪に、古めかしいスーツを着た初老の男性。彼だけが何か孤独そうに見えた。ふと目が合うと、老紳士は小さく頷いた。
「あの方は?」私は小声で渋井さんに尋ねた。 「ああ、佐伯先生だよ。月島小学校の元校長先生でね、もう20年以上、毎週金曜日の夜に一人で来るんだ」
私は興味を持った。毎週同じ曜日に同じ店に来る。それが20年以上も続いているというのは、単なる習慣を超えた何かがあるはずだ。
そのうち、カウンターに空席ができると、佐伯さんが自分の杯を持ってそちらに移動してきた。渋井さんは何も言わずに、彼の前に熱燗を注いだ。
「いつもの」というと、渋井さんは頷き、厨房に消えた。
「失礼ですが、佐伯さんですか?」 私が声をかけると、老紳士は穏やかな表情で答えた。 「そうです。あなたは?」 「いさかやと言います。居酒屋について書いているライターです」
「ほう、ライター」佐伯さんは感心したような声を出した。「それは面白い。この月島の居酒屋について何か?」
「はい。特に長く続いている老舗に興味があって」 「それなら、おばちは素晴らしい取材先ですよ。渋井君のところは味も接客も一級品です」
佐伯さんの前に、焼いた子持ちカレイの煮付けが運ばれてきた。それは渋井さんの「いつもの」だったようだ。
「あなたはずいぶん長くこの店に通われているそうですね」 「ええ、20年以上になりますかね」
私は少し考えてから、思い切って尋ねた。 「どうして毎週金曜日なんですか?」
その質問に、佐伯さんの表情が一瞬だけ曇った。彼は熱燗をゆっくりと口に運び、それから静かに答えた。
「私の妻が亡くなったのが金曜日でしてね。最後に一緒に食事をしたのもこの店だったんです。その日、私は学校の用事で遅れて、彼女を長く待たせてしまった。翌日彼女は突然倒れて…」
佐伯さんは言葉を切った。私は質問を後悔した。
「すみません、余計なことを」 「いいんです」佐伯さんは穏やかに笑った。「もう随分経ちますから。今では彼女との最後の思い出の場所として、毎週ここに来るのが私の楽しみなんですよ」
佐伯さんは子持ちカレイを丁寧に箸で裂き、一口食べた。 「妻はこのカレイが大好きでした。最後の夜も、これを食べていましたよ」
その瞬間、私は居酒屋という場所の持つ意味の深さを感じた。それは単に酒を飲み、食事をする場所ではない。人々の思い出や人生が交錯する、特別な空間なのだ。
「佐伯先生、また魚拓の話を聞かせてよ」 突然、隣の席から声がかかった。中年のサラリーマン風の男性だ。
「ああ、鈴木君。今日も残業かい?」 「ええ、ちょっとね」 鈴木という名のサラリーマンは、私に向かって説明した。 「先生は昔、趣味で魚釣りをやっていてね。壁の魚拓のほとんどは先生が寄贈したものなんですよ」
私は壁を見回した。確かに、様々な大きさの魚拓が壁一面に飾られている。中には相当な大物もあるようだ。
「そうなんですか?」 「ああ」佐伯さんは少し照れたように笑った。「若い頃は毎週末釣りに出かけていましてね。妻と知り合ったのも釣り船の上だったんですよ」
佐伯さんは昔話を始めた。彼が若い教師だった頃、趣味の釣りで出会った女性と恋に落ち、結婚した物語。そして二人で一緒に過ごした月島での日々の思い出。
話を聞いているうちに、店内の雰囲気が変わっていくのを感じた。カウンターに座る人々が、自然と佐伯さんの話に耳を傾けている。渋井さんも厨房から出てきて、時折相槌を打ちながら聞き入っていた。
「あのね、月島が埋め立てられる前は、ここら辺は全部海だったんだよ。明治時代に埋め立てられてからも、水との結びつきが強い街でね。だからこそ、魚料理が美味しい店が多いんだ」
佐伯さんの話は月島の歴史へと移っていった。明治時代の埋め立て、戦前戦後の労働者の街としての発展、そして近年のタワーマンション建設による変化。彼の人生と街の変遷が重なり合う。
鈴木さんが言った。「先生の話、いつ聞いても面白いよ。俺なんか月島に住んで15年だけど、先生の話を聞くと、もっと昔からここにいたような気分になる」
佐伯さんは照れくさそうに笑った。「長生きの特権かな」
そのとき、店の扉が開き、若い女性が一人入ってきた。 「お父さん、ここにいたの?」
佐伯さんの表情が明るくなった。「菜穂、どうしたんだい?」 「心配したのよ。電話に出ないから」 「すまない。電話は店に預けているんだ」
菜穂さんは私たちに軽く会釈すると、佐伯さんの隣に座った。 「今日も昔話?」 「ああ、ちょうどお母さんとの思い出話をしていたところだよ」
菜穂さんは微笑んだ。「またですか。私、小さい頃からその話、何度聞いたことか」 しかし、その言葉には非難の色はなく、どこか優しさがあった。
「お嬢さんですか?」私が尋ねると、佐伯さんは誇らしげに答えた。 「そうです。一人娘です。今は医者をしています」
「お父さん、もう遅いわよ。家に帰りましょう」 菜穂さんは優しく促した。佐伯さんは少し残念そうな顔をしたが、頷いた。 「そうだね。今日はもう帰ろうか」
彼は懐から財布を取り出そうとしたが、渋井さんは手を振った。 「今日は結構です。お嬢さんがわざわざ迎えに来てくれたんだから、早く帰ってください」
「いやいや、それは悪い」 「気にしないでください。また来週来てくださいよ」
やや押し問答の末、佐伯さんは渋井さんの好意を受け入れた。立ち上がる前に、彼は私に向き直った。
「若いライターさん、居酒屋について書くなら、ぜひこれを忘れないでほしい。居酒屋は単なる飲食店ではない。人々の記憶が集まる場所なんだよ。この煙とにおいの中に、どれだけの人生が刻まれていることか」
佐伯さんと菜穂さんが帰った後も、彼の言葉は私の心に残った。月島の路地裏の小さな居酒屋。そこには単なる酒と料理だけでなく、人々の思い出と記憶が染み込んでいる。
渋井さんが新しい熱燗を運んできた。 「佐伯先生のことは、どう書いても構わないよ。彼は昔から、自分の話が誰かの役に立つなら嬉しいって言ってる人だから」
「店主さんは、佐伯さんのことをよく知っているんですね」 「ああ、彼が校長先生だった頃、私の息子が月島小学校に通ってたからね。それに…」
渋井さんは少し言葉を探るように間を置いた。
「実は佐伯先生の奥さん、美代子さんが亡くなった日、二人が最後に食事をしたのはここじゃないんだ」
「え?」 「別の店なんだよ。当時私はまだここを継いだばかりでね。彼らがよく行ってたのは、もう少し先にあった『さかい』という店。でもその店は10年前に閉店して、今はない」
私は混乱した。「でも、佐伯さんは…」 「ああ」渋井さんは静かに頷いた。「佐伯先生は奥さんを亡くした後、少し…記憶が混乱するようになったんだ。でもだんだん、ここが彼らの最後の食事の場所だという記憶に変わっていった」
「それで毎週来ているんですか?」 「最初は彼の娘さんが心配して連れてきたんだ。でも、ここで過去の話をすることが彼の心を落ち着かせるようで。それに、みんなも彼の話が好きだしね」
渋井さんは壁の魚拓を見上げた。 「あれも本当は彼が釣ったものじゃないよ。でも、彼がそう言い始めたとき、誰も否定しなかった。それが彼にとって大事な記憶になっているからね」
その夜、私はカウンターに座りながら、居酒屋という空間の不思議な力について考えていた。それは時に人々の記憶を包み込み、優しく守る場所でもあるのだ。
閉店間際、最後の客として店を出ようとしたとき、渋井さんが声をかけてきた。 「よかったら、これを見ていってよ」
渋井さんが差し出したのは、古いアルバムだった。それを開くと、月島の古い写真が収められていた。埋め立て直後の様子、戦後の復興期の姿、そして今は亡き「さかい」の写真も。
「月島の居酒屋について書くなら、こういう昔の話も入れてみるといいよ。この街には語られていない物語がたくさんあるからね」
私はアルバムを丁寧に閉じ、渋井さんに返した。 「ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます」
店を出て、月島の夜の路地を歩きながら、私は考えていた。居酒屋は単なる飲食店ではない。それは人々の記憶と時間が交錯する特別な場所。煙とにおいの中に、数え切れないほどの物語が眠っている。
もんじゃストリートの喧騒も、タワーマンションの明かりも、どこか遠くに感じる静かな夜だった。明日は別の居酒屋を訪ねよう。月島の路地には、まだ知られていない物語が潜んでいるはずだ。
佐伯さんの言葉が耳に残る。 「居酒屋は人々の記憶が集まる場所なんだよ」
そして、その記憶の一部に、今夜の私の体験も加わったのだろう。