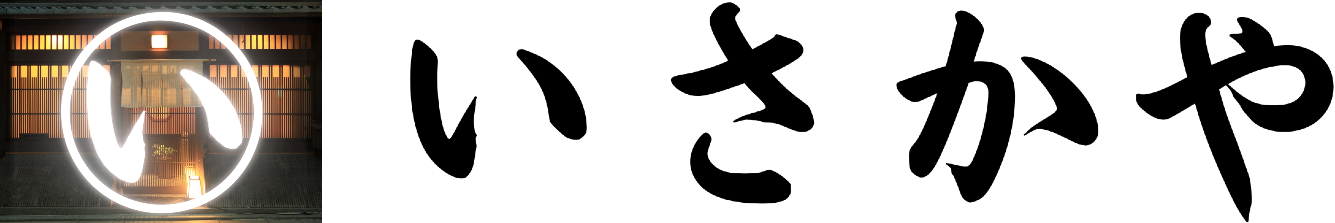※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
雨上がりの夜、高田馬場駅の東口を出ると、湿った空気に混じって様々な料理の香りが漂ってきた。早稲田大学の学生たちが行き交う駅前の雑踏を抜け、私は少し入り組んだ路地に足を踏み入れる。
私、いさかやは居酒屋ライターとして様々な街の飲み屋を巡ってきた。今夜の目的地は、友人から「絶対に行くべき」と勧められた高田馬場の小さな居酒屋だ。
「この街は学生と酒と青春が交わる場所。でも最近は、もっと多彩な色を持ち始めているんだ」
そう言った友人の言葉が気になって、私は高田馬場の居酒屋を取材することにした。
路地をしばらく歩くと、小さな赤提灯が目に入った。「ヤンゴンの風」という看板。ミャンマー語で「こんにちは」という意味の言葉が添えられていたことを、事前の調査で知っていた。ここ高田馬場は近年、「リトルヤンゴン」とも呼ばれるほどミャンマーからの移住者が多い街なのだ。
ガラス戸を開けると、異国の音楽が静かに流れる店内が広がっていた。カウンターとテーブル席が数卓。壁には色鮮やかなミャンマーの風景写真や工芸品が飾られている。
「いらっしゃいませ」
カウンターの奥から、日本語の挨拶が聞こえてきた。店主は30代半ばくらいのミャンマー人男性。にこやかな表情で私を迎えてくれた。
「初めてですか?」 「はい、友人に勧められて」 「ありがとうございます。どうぞお座りください」
カウンターに座ると、日本の居酒屋でよく見るメニューと共に、見慣れない料理の写真が並んだメニューも渡された。
「おすすめは何ですか?」と尋ねると、店主は嬉しそうに微笑んだ。 「まずはこれを」
そう言って店主が出してくれたのは、ミャンマービール「ミャンマー」の瓶と小さな前菜だった。
「これはラペットウという茶葉のサラダです。ミャンマーでは、もてなしの料理です」
ビールを一口飲み、その前菜を口に入れると、予想外の食感と風味に驚いた。発酵させた茶葉に、揚げたニンニクやピーナッツ、干しエビなどが混ざり、酸味と旨味、そして食感の複雑な調和が口の中で広がる。
「すごく独特ですね、でも美味しい」 「ありがとうございます。実はこの店、最初は日本の居酒屋だったんです」
店主のウィンさんは流暢な日本語で語り始めた。彼は10年前に留学生として来日し、高田馬場の日本語学校に通っていたという。学生時代はアルバイトとして居酒屋で働き、日本の食文化に魅了された。そして数年前、この店の前のオーナーから店を譲り受けたのだという。
「最初は普通の居酒屋をやるつもりでした。でも高田馬場にはミャンマー人が多いし、日本人にもミャンマー料理を知ってほしかった。それで、居酒屋スタイルのミャンマー料理店を始めたんです」
店内を見渡すと、数組の客がいた。日本人の学生グループ、おそらくミャンマー人と思われる若者たち、そして一人で静かに飲む中年の日本人男性。多様な客層が、このカラフルな空間に共存していた。
ウィンさんの勧めで、次に頼んだのは「モヒンガー」。ミャンマー風の魚のスープ麺で、日本のラーメンよりもとろみがあり、独特の香辛料の香りが広がる。それと、「シャン風焼き鳥」という料理。一見すると日本の焼き鳥に似ているが、レモングラスやパクチーなどの香草でマリネされた味付けが新鮮だ。
「これ、すごく美味しいですね」 「ありがとうございます。実は焼き鳥の焼き方は、学生時代にバイトしていた高田馬場の『鳥やす』で学んだんですよ」
ウィンさんによれば、高田馬場の居酒屋文化は長い歴史を持つという。特に「鳥やす」のような昭和から続く老舗は、学生や地元の人々に愛されてきた。そして最近は、彼のような新しい世代が、伝統を受け継ぎながらも独自の解釈を加えた店を開いている。
「高田馬場は、学生の街であり、多文化の街。そして何より、人と人がつながる街なんです」
ウィンさんの言葉に、私は頷いた。確かに高田馬場は、早稲田大学をはじめとする学生街として知られるが、それだけではない。昭和の風情を残す老舗居酒屋と、ミャンマーやタイ、韓国などのアジア各国の料理店が混在し、独特の多文化空間を形成している。
カウンターで一人飲んでいた中年男性が、私たちの会話に耳を傾けていたらしく、自己紹介してきた。 「すみません、お話聞いてました。私、吉田と言います。実は早稲田の卒業生で、昔からこの辺りの居酒屋によく来てるんですよ」
吉田さんは40代後半の編集者で、学生時代から高田馬場の居酒屋を巡るのが趣味だという。
「僕が学生だった頃は、もっとガヤガヤした大衆酒場が主流でしたね。100円でウイスキーが飲めるような店もあって」
彼の話によれば、90年代の高田馬場は、もっと「学生街」色が強かったという。安く酔えることが最優先で、焼き鳥や串カツ、唐揚げなどの定番メニューを提供する店が並んでいた。そして校歌を歌いながら酔う学生たちで賑わっていたのだ。
「でも、こういう店も増えてきて、街が変わってきた。いい意味で国際的になりましたね」
吉田さんはそう言いながら、ウィンさんの出してくれた「モンティ」という蒸留酒を少しずつ楽しんでいた。その香りは日本の焼酎とも異なる、独特の風味だ。
「このお酒、最初は慣れなかったけど、今では好きになりましたよ。これを飲みに、週に1回は来てます」
彼の言葉に、ウィンさんは嬉しそうに笑った。「吉田さんは常連さんです。彼のおかげで、メニューにも日本人向けの工夫ができました」
私が取材していることを知った吉田さんは、高田馬場の居酒屋について熱心に語ってくれた。
「高田馬場の居酒屋の特徴は、なんと言っても多様性ですね。昭和から続く老舗焼き鳥屋、立ち飲み、ジビエ料理の専門店、日本酒にこだわる店、そして最近はこういうアジア系の店も増えてきた」
彼の説明によれば、高田馬場は「飲み歩き」の文化も根付いているという。1軒目は定番の居酒屋、2軒目は少し変わった店、3軒目はラーメンかアジア料理…というように、自然と流れ歩く楽しみ方が普通だそうだ。
「特に学生たちは予算が限られてるから、いろんな店をはしごするんです。僕も学生の頃はそうでした」
話をしているうちに、店内はさらに賑わってきた。日本人とミャンマー人が交互に乾杯する光景は、まるで国境のない空間のようだ。言葉は通じなくても、「カンパイ!」と「チェーズー!」という掛け声だけは共通している。
「実は今度、高田馬場の居酒屋マップを作ろうと思ってるんです」とウィンさんが言った。「日本人にもミャンマー人にも、この街の多様な飲み屋を知ってほしくて」
その言葉を聞いて、私は思わず提案した。「それなら、記事にしませんか?私が取材協力します」
そうして私たちは、翌日から高田馬場の居酒屋巡りを始めることになった。
翌日の午後、私たちは高田馬場駅で待ち合わせた。ウィンさんと吉田さん、そして吉田さんが呼んだという早稲田大学の学生、田中くんも一緒だ。「四世代で巡る高田馬場の居酒屋」という企画が、即興で始まった。
最初に向かったのは、ウィンさんが修行したという「鳥高」。1970年創業の老舗で、カウンターの向こうでは、白髪の親父さんが黙々と焼き鳥を焼いていた。その技術は無駄がなく、長年の経験が生み出す完璧な焼き加減だ。
「ここの西京焼きが最高なんです」と吉田さん。注文してみると、たしかに絶妙な甘さと香ばしさのハーモニーが口の中に広がった。
「私、この味を参考にしたんですよ」とウィンさんが小声で言う。彼の店の「シャン風焼き鳥」のベースは、ここにあったのだ。
次に向かったのは、「海井戸」という立ち飲み屋。100円台からのおつまみと、手頃な価格の日本酒が楽しめる店だ。平日の夕方だというのに、すでに学生やサラリーマンで賑わっていた。
「ここは予算が限られている学生の味方なんです」と田中くん。「テスト週間でも、ここならコスパよく一杯飲める」
その言葉通り、この店の魅力は「安くて美味い」の一言に尽きる。刺身の盛り合わせは新鮮で、ひと皿300円という破格の値段だ。
3軒目は、吉田さんのお気に入りという「黄龍」。酒蔵直営の居酒屋で、日本酒の品揃えが圧巻だ。壁一面に並ぶ日本酒のボトルは、まるで美術館のよう。そして料理も、季節の魚や野菜を使った創作メニューが多彩だ。
「ここは学生にとっては少し贅沢な店かもしれませんが、特別な日に来るんです」と吉田さん。「僕も就職が決まった日、ここで祝杯を挙げました」
そんな思い出話を聞きながら、私たちは「ロマネスコのツナマヨ和え」や「特大おにぎり」などの名物料理を堪能した。
最後に訪れたのは、タイ料理と日本の居酒屋文化が融合した「バーンサバイ」という店。ここでは、トムヤムクンベースの鍋や、タイハーブを使った焼き鳥など、創作メニューが楽しめる。店主は日本人だが、タイに長く住んだ経験があり、本場の味と日本人の好みを絶妙にブレンドしているという。
「高田馬場って、こんなに多様な店があるんですね」と私。 「それが魅力なんです」と吉田さん。「どんな人でも、自分の居場所が見つかる街なんです」
日が暮れて、私たちは再びウィンさんの店「ヤンゴンの風」に戻った。今夜の取材は終わったが、彼らとの対話はまだまだ続く。
「今度はミャンマー料理教室もやろうと思ってるんです」とウィンさん。「日本人に、もっとミャンマーを知ってほしくて」
その言葉に、田中くんが食いついた。「僕、参加したいです!実は卒業研究で、多文化共生について調べているんです。高田馬場を事例として」
「それなら、僕も力になれるかも」と吉田さん。「出版社のコネを使って、その研究を小冊子にできるかもしれない」
私もまた、彼らの会話に引き込まれていった。「私も記事を書きますよ。高田馬場の居酒屋文化と多文化共生の物語として」
こうして、四人の異なる背景を持つ人間が、居酒屋というフィールドで新しいプロジェクトを生み出そうとしていた。まさにこれこそが、高田馬場の居酒屋の持つ力なのかもしれない。
1ヶ月後、私たちの共同プロジェクト「高田馬場・酒と食の多文化地図」が完成した。田中くんの研究をベースに、吉田さんの編集、ウィンさんのコミュニティネットワーク、そして私の取材記事が一つになった小冊子だ。高田馬場のおよそ50軒の居酒屋が、そのルーツや特徴、店主のストーリーとともに紹介されている。
「ヤンゴンの風」での完成披露パーティには、様々な店の店主や常連客、学生たちが集まった。日本人、ミャンマー人、タイ人、韓国人…多様な顔ぶれが、一つの空間に集まり、それぞれの言葉で乾杯した。
ウィンさんが皆の前で語った。 「高田馬場は、私にとって第二の故郷です。この街の居酒屋は、単に酒を飲む場所ではなく、文化が交わる場所。そして何より、人と人がつながる場所なんです」
彼の言葉に、会場から大きな拍手が湧き起こった。
その夜、私は取材ノートに最後の一文を記した。
「高田馬場の居酒屋は、学生の街の喧騒と、異国の香りが混ざり合う不思議な空間だ。そこでは、年齢も国籍も関係なく、人と人とが酒と食を通じてつながっていく。それは、これからの日本の姿を小さく映し出す鏡のようだ」
帰り際、ウィンさんが私に言った。 「いさかやさん、また来てくださいね。次回は、もっと面白い話があります」
私は笑顔で頷いた。この街の物語は、まだ始まったばかりなのだから。