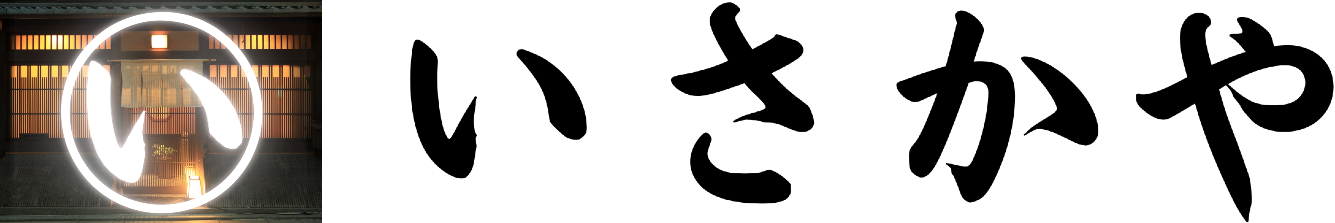昭和三十年代、東京の下町。まだ高層ビルが少なく、路地裏には人情が溢れていた時代。「いさかや」はそんな古き良き昭和の風景の中で、ひっそりと営まれていた小さな食堂だった。
駅から十分ほど歩いた住宅街の中にある「いさかや」。表通りからは一本入った路地にあり、昔ながらの木造二階建て。軒先には赤い提灯が一つ、「いさかや」と墨書きされた文字が風に揺れている。そうとは知らなければ、普通の民家と見間違えるほどの佇まい。
私の祖父・武志は、この「いさかや」の常連だった。戦後まもなく東京の復興に関わり、その後も町工場を営んできた人だ。祖父が他界して十年経った今、私は祖父の日記を整理していて、何度も登場する「いさかや」という名前に興味を持ち、訪ねてみることにした。
驚いたことに、祖父の日記に記されていた通りの場所に、今もなお「いさかや」は存在していた。時代は令和になっても、建物はほとんど変わっていない。
戸を開けると、懐かしい出汁の香りが漂ってきた。店内は六畳ほどの広さで、カウンター席が五つと、小上がりに二つのテーブル。カウンターの後ろには昭和の映画スターのブロマイドが並び、天井からはちょうちんが下がり、どこか懐かしい雰囲気を醸し出している。
「いらっしゃい」
カウンターから聞こえた声に目を向けると、七十代と思われる女将さんが立っていた。白髪を丁寧に結い上げ、渋い色の割烹着を身につけている。
「あの、こちらのお店について調べているんですが…」
「あら、調査かい?」女将さんは少し首を傾げた。
「祖父が常連だったみたいで…」
「お爺さんのお名前は?」
「佐藤武志といいます」
女将さんの目が見開かれた。
「武ちゃんの孫かい!」
思いがけない反応に私は驚いた。女将さん、本名・加藤みどりさんは、祖父の若い頃からの知り合いだという。
「座りなさい、座りなさい。あんたのお爺さんのことなら、いくらでも話せるよ」
そうして、私は昭和の香りが漂う「いさかや」で、祖父の知られざる一面を知ることになった。
みどりさんの話によると、「いさかや」は昭和二十二年(1947年)の創業。みどりさんの父親が戦地から戻り、細々と始めた食堂だった。当時は物資も乏しく、できる料理も限られていたが、安くて美味しいと評判になり、近所の人々の憩いの場となっていった。
「いさかや」の名前の由来は、創業者の「伊坂」という苗字からきているが、酒を出さない食堂だったことから、敢えて「居酒屋」とは書かずに「いさかや」としたのだという。
祖父・武志がこの店に通い始めたのは、昭和二十五年頃。東京の復興事業に関わる仕事で、この界隈に来るようになってからだ。
「武ちゃんはね、毎週木曜の夜には必ず来てたよ」みどりさんは懐かしそうに語る。「仕事帰りに寄って、いつも同じものを注文してた。肉じゃがに味噌汁、それからご飯大盛り」
武志は当時、まだ独身で、下宿先の食事があまり口に合わなかったらしい。「いさかや」の家庭的な味に惹かれ、足繁く通うようになった。
「それで、ある日のことよ」みどりさんは目を細めた。「武ちゃんが、いつもと違う女の子を連れてきたの。それが武ちゃんの奥さん、あんたのお祖母ちゃんよ」
私の祖母・貞子は、祖父が働いていた会社の経理係だった。二人が出会ったのは昭和二十八年。祖父は祖母を口説くために、わざわざ「いさかや」に連れてきたという。
「お祖母ちゃんも喜んでたわよ。『こんな美味しいお店があったなんて』って」
私は祖母の話を聞いて微笑んだ。祖母は料理上手だったが、家庭料理を大切にする人だった。きっと「いさかや」の素朴な味に共感したのだろう。
みどりさんは立ち上がると、カウンターの下から古いアルバムを取り出した。そこには昭和三十年代の「いさかや」の写真が収められていた。
「ほら、これが武ちゃんと貞ちゃん」
モノクロ写真の中には、若かりし日の祖父母が並んで座り、笑顔で杯を上げている姿があった。祖父の顔は初々しく、祖母は少し照れたような表情を浮かべている。
「この写真、昭和三十三年の暮れ。武ちゃんが町工場を始めると決めた日の写真よ」
祖父の町工場「佐藤製作所」は、私が子供の頃まで続いていた。家族を養い、二人の子供(私の父と叔父)を大学まで行かせた。その決断の日が「いさかや」だったとは。
「あの日ね、武ちゃんは『おばちゃん、俺、自分の工場を持とうと思うんだ』って言ったの。貞ちゃんも一緒に来てて、二人で将来の夢を語り合ってた」
みどりさんの話を聞くうちに、私の脳裏には昭和の「いさかや」の情景が浮かんできた。赤い提灯の灯り、囲炉裏の温もり、人々の笑い声。そこに若き日の祖父母がいる。
「武ちゃんはね、この店を『第二の実家』って呼んでたよ」みどりさんは続けた。「結婚して子供ができても、何かあるたびに来てた。息子さんたち(私の父と叔父)も連れてきてたわよ」
私は父に「いさかや」の話を聞いたことがなかった。聞いてみると、父も子供の頃に何度か来たことがあるというが、詳しい記憶はないとのこと。
みどりさんはさらに話を続けた。
「昭和四十年代になると、この辺りも随分変わってきてね。古い家が壊されて、マンションが建ち始めた。でも武ちゃんは『いさかやだけは変わらないでほしい』って言ってた」
実際、「いさかや」の周囲は高層マンションや新しい商業施設に囲まれるようになったが、この建物だけは昭和の面影を残している。
「うちはね、立退き話もあったのよ。でも父さん(みどりさんの父親)が『この店には思い出がある』って頑として譲らなかった。武ちゃんも応援してくれてね、法律の知識を貸してくれたり、町内会で話してくれたり」
祖父は地域の発展と古き良きものの保存の両立を考えていたのだろう。日記にも町の変化を嘆きつつも、進歩の必要性を認める記述があった。
「それで、昭和五十年代になってからは、武ちゃんは『いさかやの会』というのを始めたのよ」
「いさかやの会?」
「そう、月に一度、この店に集まって、町の未来を語り合う会。商店街の人や町工場の経営者、それからお役所の人なんかも来てたわ」
祖父の日記にも「いさかやの会」の記述があった。しかし、単なる飲み会だと思っていたのだ。
「あの会があったからこそ、この辺りの再開発も上手くいったんじゃないかな。みんなの意見を聞いて、調整して…武ちゃんは橋渡し役が上手だったからね」
私は祖父がそんな役割を担っていたとは知らなかった。家族には「頑固な職人」としか見えていなかったのに。
「でもね」みどりさんは少し寂しそうな表情を見せた。「平成になると、武ちゃんの姿も少なくなってきたの。体調が優れなくなってきたのかな」
祖父は平成十五年に他界した。晩年は確かに体調を崩しがちだった。
「最後に来たのは亡くなる二ヶ月前かな。いつもの肉じゃがを食べて、『みどりちゃん、ありがとう。この味は変わらないね』って言ってた」
みどりさんの言葉に、私の目に涙が浮かんだ。
「いさかやの記憶」、それは祖父が大切にしていた昭和の風景であり、人々の絆だったのだ。
「あんたにも何か食べていってもらおうか」みどりさんは立ち上がった。「武ちゃんの孫なら、肉じゃがでいいかい?」
「はい、お願いします」
みどりさんが厨房に立つ姿を見ながら、私は祖父の日記を開いた。そこには昭和四十二年の一節があった。
「今日もいさかやで一杯やった。この味、この場所が変わらないことを願う。時代は変わっても、人の心は変わらない。いさかやはそんな場所だ」
やがて運ばれてきた肉じゃがは、素朴で温かい味だった。じゃがいもはほくほくと柔らかく、肉は優しい出汁に浸かり、甘辛く煮含められている。一口食べると、懐かしい気持ちになった。一度も食べたことがないはずなのに、どこか記憶の奥底に残っているような味。
「おばあちゃんの味に似てるね」思わず口に出した。
「そうでしょ?」みどりさんは嬉しそうに笑った。「貞ちゃんはね、『この味を家でも作りたい』って言って、うちの父さんから教わったのよ。だから、あんたのおばあちゃんの味は、元はといえばいさかやの味なんだよ」
それを聞いて、私は祖母の料理を思い出した。確かに祖母の肉じゃがは、素朴でありながら深い味わいがあった。祖母から母へ、そして時々私も作る肉じゃがのレシピ。その源流がここにあったとは。
「いさかや」の味は、こうして三世代にわたって受け継がれていたのだ。
食事を終え、会計をしようとすると、みどりさんは首を振った。
「今日は武ちゃんの分だと思って、おごりよ」
「そんな…」
「いいの、いいの。でも、また来てよ。武ちゃんみたいに、月に一度でもいいから」
私は頷いた。「はい、必ず来ます」
帰り際、みどりさんは一枚の写真をくれた。アルバムにあった祖父母の写真のコピーだ。
「これ、持っててね。武ちゃんと貞ちゃんの若かりし日の思い出だから」
路地を出て振り返ると、赤い提灯が夕暮れの中で静かに揺れていた。「いさかや」。その名前は今も昭和の記憶を映す鏡のように、静かに時を刻んでいる。
後日、私は父と叔父を「いさかや」に連れていった。彼らも久しぶりの訪問に感慨深げだった。みどりさんは大喜びで、昔話に花を咲かせた。
それからというもの、私たち家族は「いさかや」との縁を新たにした。父はみどりさんから聞いた「いさかやの会」を現代版として復活させ、地域の課題について語り合う場を作った。叔父は祖父の町工場を継いでいるが、後継者問題に悩んでいたところ、その会で若い職人と出会い、新たな展開を見出しつつある。
私は「いさかや」の歴史と祖父の思い出を記録に残すことにした。昭和の記憶が薄れゆく中で、この小さな食堂が持つ意味を伝えていきたいと思ったからだ。
時代は移り変わり、街の景色は変わっていく。しかし「いさかや」のような場所が持つ記憶と絆は、形を変えながらも受け継がれていく。
いつか東京の下町を歩いていて、赤い提灯の灯る小さな食堂を見つけたら、それは「いさかや」かもしれない。そこには昭和の面影と、人々の温かな記憶が今もなお息づいているだろう。
時が経っても変わらない味、変わらない場所の大切さを教えてくれる「いさかや」の物語は、これからも続いていく。