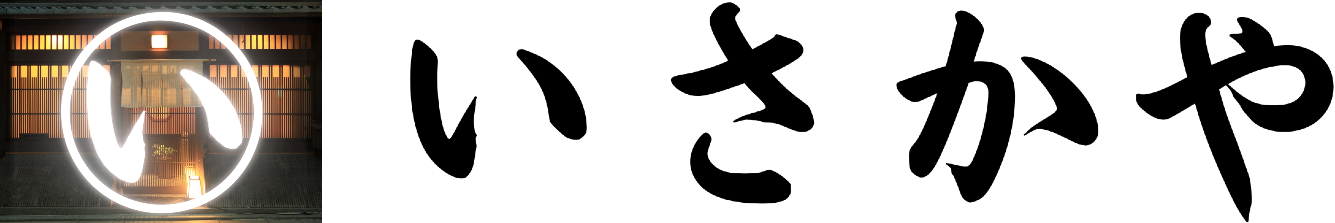※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
東京の冬の夜は、やけに冷たい。
ビルの谷間を吹き抜ける風が頬を撫で、私は首元のマフラーを引き上げた。新宿の街はいつものように人でごった返している。会社帰りのサラリーマン、待ち合わせの若者たち、観光客、そして夜の街で働く人々…あらゆる人が入り混じる、東京の縮図のような場所だ。
私、いさかやは居酒屋ライターとして全国の飲み屋を回っている。特に都市部の居酒屋文化を追いかけ、その街独特の「酒と人」の物語を記事にしている。今夜の目的地は新宿ゴールデン街。その混沌とした迷宮のような路地に並ぶ、小さな酒場を訪ねる予定だった。
「この世界には、忘れられない酒場というものがある」
そう思いながら私は歩を進めた。世界的に見ても珍しい飲み屋街、ゴールデン街。終戦直後の闇市が起源とされ、当時の都市計画の狭間で取り残されたような不思議なエリア。一坪二坪ほどの小さな店が無数に並ぶ、異空間のような場所だ。
ゴールデン街の入口に差し掛かると、狭い路地に赤や黄色の明かりが灯っていた。店の看板はどれも個性的で、外国人観光客が写真を撮っている。昭和の風情を残すこの街は、今や新宿の観光スポットにもなっている。
私が向かったのは「月の記憶」という小さな酒場。ドアを開けると、そこには昭和の空気が凝縮されたような空間が広がっていた。カウンターが8席ほど。奥にテーブル席が2つ。壁には古い映画のポスターや、黄ばんだ写真が所狭しと貼られている。
「いらっしゃい」
カウンターの中から声がかかった。マスターは60代半ばくらいの男性で、白いシャツに黒いベストという出で立ち。まるで映画に出てくるバーテンダーのような佇まいだ。
「お一人様ですか?」
「はい」
「カウンターどうぞ」
店内にはすでに数人の客がいた。カウンター席には中年のサラリーマン風の男性が一人。テーブル席には外国人観光客らしきカップルと、演劇関係者らしき若者たちのグループ。
私がカウンターに腰掛けると、マスターが水とおしぼりを出してくれた。
「何にします?」
「まずは生ビールを」
「かしこまりました」
マスターは無駄のない動きでビールを注いだ。泡の立て方も絶妙で、長年の経験が感じられる。
「ここで飲むのは初めてですか?」と、マスターが尋ねてきた。
「はい。居酒屋の記事を書く仕事をしていて、ゴールデン街を取材中なんです」
「なるほど」
マスターは少し考えるような素振りを見せた後、続けた。
「この街は特別ですよ。特に昔は作家や画家、映画監督、俳優…そんな文化人たちのたまり場でした。今でも演劇人や音楽家が多いですね」
その言葉通り、店内からは演劇の話をする若者たちの声が聞こえてくる。彼らはおそらく劇団員か演出家の卵だろう。熱のこもった声で台本や演出について語り合っていた。
「新宿の居酒屋文化は深いですね」と、私が言うと、マスターは笑った。
「それを語るなら一晩じゃ足りませんよ。新宿はね、戦後の闇市から始まったんです。あの頃は焼け野原だった駅前に、様々な人が集まって闇市を形成した。そこで酒と食料を売る店が自然発生的に増えていった。特に思い出横丁、昔は『しょんべん横丁』って呼ばれてましたけど、あそこが象徴ですね」
マスターの話は歴史の教科書のようだった。私は生ビールを飲みながら、メニューを見ていると、「おすすめは?」と尋ねた。
「そうですね…まずは刺身の盛り合わせと、うちの名物『月の酒肴』あたりはどうですか」
注文すると、マスターは手早く料理を作り始めた。しばらくすると、美しく盛り付けられた刺身の盛り合わせと、見たことのない前菜の盛り合わせが運ばれてきた。
「これが『月の酒肴』です」
皿の上には、小さく切られた白い何かが、月のような円を描くように盛り付けられていた。それを一口食べると、柔らかな食感と共に、酸味と甘み、そして魚介の旨味が広がる。
「これは何ですか?」
「烏賊と蛸を特製の調味液に漬け込んだものです。このレシピは三島由紀夫が好んで食べていたと言われているんですよ」
ゴールデン街には、そんな文化人の逸話が今も息づいていた。
マスターは料理を出しながら、新宿の居酒屋の話を続けた。
「新宿の居酒屋は、エリアによって全く性格が違うんです。思い出横丁は昭和レトロ、歌舞伎町はカオス、ここゴールデン街は文化人の街。南口や東南口周辺は比較的新しいおしゃれな店が多いですね」
私がメモを取りながら聞いていると、隣に座っていたサラリーマン風の男性が会話に参加してきた。
「僕はもう20年以上、この店の常連なんですよ」
男性は自己紹介した。名前は佐藤、出版社で働いているとのこと。仕事帰りにほぼ毎日、このゴールデン街に立ち寄るという。
「この街の良さは、一人でも気兼ねなく飲めること。それと、普通なら接点のない人と会話できることかな。僕なんか、ある日ここで飲んでいたら、好きな作家さんが隣に座ってて。思わず話しかけたら、一緒に飲むことになって…」
佐藤さんは目を輝かせながら、ゴールデン街での思い出を語り始めた。確かに新宿、特にこのゴールデン街には「偶然の出会い」や「一期一会」の文化があるのかもしれない。
マスターが新しい料理を運んできた。「これは季節のおすすめです」と言って、キノコと地鶏の炊き込みご飯を出してくれた。シンプルな料理だが、香りが食欲をそそる。
「新宿の居酒屋で面白いのは、24時間酒が飲める店があることですね」と佐藤さんが続けた。「特に歌舞伎町には朝6時オープンの店もあって、夜勤明けの人や、これから帰る人が入り混じるんですよ。新宿は時間の概念が壊れている街なんです」
話を聞きながら私は料理を楽しんだ。どれも素朴でありながら、確かな技術を感じさせる味だ。特に刺身は鮮度がよく、口の中でとろける。
「新宿の居酒屋は、食べ物も多様性があるんですよ」とマスターが言った。「古い大衆居酒屋から、ハイエンドな高級店、24時間営業の店、外国人向けのパブ、クラフトビール専門店…本当に何でもある。それが新宿の魅力ですね」
佐藤さんは日本酒を注文し、それを私にも少し分けてくれた。「この酒、うまいでしょう?ここでしか飲めないんですよ」
私たちの会話は、ゴールデン街の店の話から、新宿の変遷、そして東京の酒文化へと広がっていった。時間が経つにつれ、店内の雰囲気もより親密になっていく。演劇人グループと外国人カップルも会話を始め、まるで皆が古くからの知り合いであるかのような空気が生まれていた。
「新宿の最大の特徴は、『はしご酒文化』かもしれませんね」と、マスターが言った。「ほとんどの人は1軒では終わらず、2軒目、3軒目と流れ歩く。それが新宿流なんです」
確かに、外を歩いていると「ちょっと一杯だけ」という気軽さで入れる店が無数にある。新宿の夜は、そうやって様々な店を巡りながら、様々な人と出会う物語なのかもしれない。
佐藤さんが時計を見て、「そろそろ次の店に行きましょうか」と私を誘った。「ゴールデン街を知るなら、いくつか店を回らないとね」
マスターに勘定を払い、私たちは店を出た。冷たい外気が酔いを少し覚ます。狭い路地には行き交う人々で溢れ、各店からは笑い声や会話が漏れ聞こえてくる。
佐藤さんは私を案内するように歩き出した。「次はあっちの店にしましょう。あそこはジャズ好きが集まる店で…」
その夜、私たちは結局5軒もの店をはしごした。どの店も個性的で、そこにいる人々もそれぞれ魅力的だった。ジャズバーでは年配のミュージシャンが、昔の新宿の話を聞かせてくれた。外国人向けの店では、日本の居酒屋文化に興味津々の観光客と交流した。最後に訪れた店は、なんと朝5時まで営業しているという居酒屋で、そこでは夜の街で働く人々が続々と入店してきていた。
気がつけば、東の空が白み始めていた。私たちはようやく店を出て、人気のない新宿の街を歩いた。普段は人で溢れる交差点も、この時間はひっそりとしている。
「新宿の魅力は、こうして一晩中飲めること、そして誰とでも友達になれること」と佐藤さんが言った。「特にゴールデン街は、小さな店が多いから、自然と隣の客と会話することになる。それが出会いを生むんだ」
彼の言葉を聞きながら、私は記事の構想を練っていた。新宿の居酒屋文化は、ただ食べて飲むだけの場所ではない。それは人々が交わり、物語が生まれる場所なのだ。
数日後、私はその夜の体験をもとに記事を書いた。「新宿ゴールデン街の灯 – 昭和から令和へ継がれる酒場の物語」というタイトルで、新宿の居酒屋文化の多様性と、そこで出会った人々の話を綴った。
記事を書き終えた夜、再びゴールデン街を訪れた。「月の記憶」のドアを開けると、マスターが笑顔で迎えてくれた。
「いらっしゃい、いさかやさん。記事はどうなりました?」
「おかげさまで完成しました。とても好評で、編集長も喜んでいます」
「それは良かった。今夜は何にしますか?」
「まずは生ビールを」
カウンターに座り、店内を見回す。いつもの佐藤さんの姿はなかったが、別の常連客たちが談笑していた。マスターがビールを注ぎながら言った。
「新宿の居酒屋の良さを知ったら、もう離れられませんよ」
その言葉に、私は笑顔で頷いた。確かに新宿の居酒屋には不思議な魅力がある。多様性と、人との繋がり、そして歴史が息づく場所。ゴールデン街の小さな灯りは、これからも様々な人々を温かく迎え続けるのだろう。
「そうですね。これからもきっと、何度でも戻ってくると思います」
私の言葉に、マスターは満足そうに頷いた。窓の外では、新宿の夜が再び始まろうとしていた。