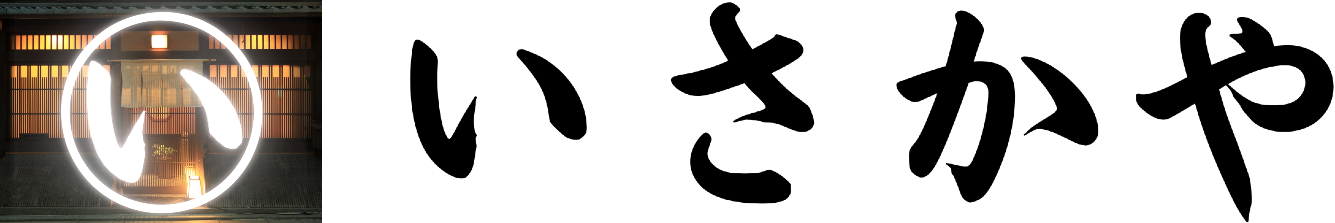空と海が溶け合う地平線の向こうから、朝日が顔を出した。遠くに見える漁船の影が、オレンジ色に染まる水面に黒いシルエットを落としている。浜辺には、昨夜の嵐で打ち上げられた海藻や貝殻が点々と散らばっていた。
私は砂浜に腰を下ろし、目の前に広がる風景を眺めていた。この漁村に来て一週間。取材のために訪れたのだが、主役である「いさかや」の噂を追う旅は、思いのほか難航していた。
私はグルメコラムニスト。東京の雑誌社で働き、全国の美食を探る仕事をしている。今回の取材テーマは「幻の味 – 伝説の海の幸を追う」。編集長から指示されたのは、「いさかや」という名の魚を求めて南の島々を巡る旅だった。
「いさかや」とは、地元の方言で「幸せの使者」を意味するという魚の名前。伝説によれば、七年に一度だけ、この村の近海に姿を現すとされている。銀色の鱗に青い斑点が散りばめられ、口元には金色の線が走っているという特徴的な姿。しかし何より特筆すべきは、その味だ。
「一度食べたら忘れられない。天国の味だ」
そう語るのは、この村で最も古い食堂「潮風亭」の主人・佐伯さんだった。七十代半ばの佐伯さんは、若い頃に一度だけ「いさかや」を口にしたことがあるという。
「あれは昭和四十二年の夏だった。七年ぶりに現れた『いさかや』を、先代から受け継いだ秘伝の調理法で料理したんだ。その味は…言葉では言い表せない」
佐伯さんの目は遠くを見つめ、半世紀以上前の記憶を辿るように輝いていた。
「それから七年ごとに現れるはずだったが、海の環境が変わってね。次の周期では姿を見せなかった。そして昨年…四十九年ぶりに再び『いさかや』が捕れたという噂を聞いたんだよ」
「誰が捕ったんですか?」と私は尋ねた。
「若い漁師さ。佐々木という名前の。あの子は…特別なんだ」
佐伯さんはそれ以上を語らなかったが、私は次なる取材対象を見つけたことに胸を躍らせた。佐々木という漁師を探し出せば、「いさかや」の謎に近づけるかもしれない。
翌朝、私は漁港で佐々木を探した。地元の人々の話によれば、彼は他の漁師たちとは少し違うという。「変わり者だが、海のことなら誰よりも詳しい」そう評されていた。
漁港の端にある小さな船着場。そこに一艘の古びた木造船が停泊していた。船体には「海神丸」と書かれている。その船の上で、一人の男が網の手入れをしていた。痩せた体に日焼けした肌、三十代半ばといったところか。
「佐々木さんですか?」と声をかけると、男は作業の手を止め、こちらを見た。
「ああ、そうだ」彼の声は意外に優しかった。「何の用だ?」
私が取材の目的を告げると、佐々木は少し警戒するような表情を見せた。
「『いさかや』のことを知りたいのか」彼は海の方を見つめながら言った。「あの魚のことは…あまり話したくないんだ」
「なぜですか?」
「話せば話すほど、その魚は遠ざかる。それがこの村の言い伝えだ」
それでも私は諦めなかった。三日間、毎朝漁港に通い、佐々木の仕事を手伝いながら彼の心を開こうと努めた。 網を引き上げ、魚を箱詰めし、船を洗う。都会育ちの私には重労働だったが、海の匂いと漁師の仕事の流れに少しずつ馴染んでいった。
四日目の夕方、佐々木は突然私に言った。
「明日、一緒に船に乗れ。『いさかや』の話をしてやる」
早朝五時、まだ星が空に残る時間に、私たちは海に出た。「海神丸」は小さいながらも、佐々木の手によって丁寧に整備されていた。エンジンの音が静かな海に響き、少しずつ陸地が遠ざかっていく。
一時間ほど進んだだろうか。佐々木はエンジンを切った。周囲には何もない。ただ青い海と空だけが広がっていた。
「ここだ」彼は言った。「『いさかや』が最後に姿を見せた場所だ」
佐々木は船の縁に腰掛け、遠くを見つめながら話し始めた。それは、私が想像していた以上に奇妙な物語だった。
「実は…『いさかや』は幻の魚じゃない。ただ、捕まえることが難しいだけだ」
佐々木によれば、「いさかや」は深海と浅海を行き来する回遊魚で、通常は水深200メートル以上の場所に生息している。それが特定の条件が揃った時のみ、浅瀬に上がってくるという。
「潮の満ち引き、水温、月の満ち欠け…さらには海流の変化。これらがすべて重なった時だけ、『いさかや』は姿を現す」
「それが七年に一度なんですか?」
「いや、もっと複雑だ。かつては七年周期だったが、気候変動で海の環境が変わり、その周期も乱れている。だから四十九年も現れなかったんだ」
「では、去年捕れたという噂は…?」
佐々木は黙って立ち上がり、船の小さな船室に入った。戻ってきた彼の手には、古びた小箱があった。
「これを見せよう」
箱を開けると、中には一枚の写真と、銀色に輝く鱗が数枚入っていた。写真には若い佐々木が、銀青色の美しい魚を抱えて笑っている姿が写っていた。
「去年の十月、ここで捕まえた。生涯で二度目の『いさかや』だった」
「一度目は?」
「子供の頃。父と一緒に船に乗っていた時だ。あの時は…」
佐々木の表情が曇った。何か言いにくそうにしている。
「どうしたんですか?」
「…あの魚には秘密がある」彼は低い声で言った。「『いさかや』を食べると、忘れていた記憶が蘇るんだ」
私は驚いて言葉を失った。佐々木は続けた。
「子供の頃、父が捕った『いさかや』を食べた夜、私は突然、生まれる前の記憶を見た。海の中にいる感覚。波の音。母の胎内にいた時の記憶だと思う」
「それは…」
「狂っていると思うだろう?でも、この村の人たちは知っている。『いさかや』には不思議な力があることを」
そして佐々木は、去年捕った「いさかや」のことを語り始めた。彼はその魚を村の誰にも見せず、一人で調理して食べたという。その夜、彼は十年前に亡くなった婚約者との記憶を、鮮明に思い出したのだ。
「彼女は津波で命を落とした。私は彼女との思い出の多くを、悲しみから無意識に封印していた。でも『いさかや』を食べたあの夜、すべてが蘇ったんだ。彼女の笑顔、声、香り…まるで昨日のことのように」
佐々木の目には涙が浮かんでいた。
「だから私は言ったんだ。あの魚のことは話したくないと。みんなが争って捕りに来るようになれば、『いさかや』はきっと二度と姿を見せなくなる」
私は黙って佐々木の言葉を聞いていた。この話を記事にすべきか、迷いが生じていた。読者の興味を引く奇妙な物語だが、この村の秘密を暴くことになる。
「佐々木さん、もし『いさかや』をもう一度捕まえることができたら、どうしますか?」
彼は海を見つめながら答えた。
「今度は…誰かと分かち合いたい」
それから二週間、私は佐々木と共に毎日海に出た。彼から漁の技術を教わり、潮の流れを読む方法を学んだ。そして、「いさかや」についての話を少しずつ聞かせてもらった。
「いさかや」の調理法は複雑だった。 鮮度が命で、捕れてから二時間以内に下処理をしなければならない。身を薄く引き、特製の塩に三十分だけ漬け、それから昆布で巻いて一晩寝かせる。翌朝、その身を桜の木で作った桶に入れ、特製の出汁に浸して食べるのが伝統的な方法だという。
「その出汁が最も重要だ」と佐々木は言った。「梅干し、昆布、鰹節、そして…秘密の一味。それが『いさかや』の味を最大限に引き出す」
私たちの海での日々は続いた。「いさかや」は現れなかったが、私は不思議と失望を感じなかった。佐々木との会話、海での時間が、この取材の本当の価値なのではないかと思い始めていた。
最後の日、私たちは普段より遠くまで足を伸ばした。天気は良く、海は穏やかだった。
「『いさかや』は今日も来ないだろう」佐々木は言った。「でも、別の素晴らしい魚はきっと捕れる」
その言葉通り、その日私たちは豊漁だった。新鮮な魚を抱えて村に戻ると、佐々木は私を自分の家に招いた。
「最後の夜は、私が料理をごちそうしよう」
佐々木の家は漁港の近くにある質素な一軒家だった。中に入ると、意外なほど清潔で整然としている。彼は手際よく魚を捌き始めた。
「『いさかや』ではないが、この魚も美味いぞ」
彼が作る料理は素朴ながらも丁寧で、魚本来の味を大切にしていた。その姿勢は「いさかや」への接し方と同じだった。
食事をしながら、私は取材の成果をどうするか佐々木に相談した。
「記事は書きますが、『いさかや』の正確な場所や捕り方は書きません。ただ、その魚と村の伝統、そして…あなたの想いを伝えたいと思います」
佐々木は黙って頷いた。
「それともう一つ」私は続けた。「もし機会があれば、私も『いさかや』を味わってみたいです」
彼は微笑んだ。「いつか必ず。その時は連絡する」
翌朝、私は村を離れた。東京に戻り、「いさかや」についての記事を書き上げた。しかし、出版前に一つの決断をした。幻の魚の具体的な特徴や捕れる条件、正確な場所などは敢えてぼかしたのだ。
「いさかやの海 – 記憶を呼び覚ます幻の味」というタイトルの記事は、幻想的な魚の物語として発表された。読者の反応は上々で、編集長も満足していた。
それから一年が経った今日、私の元に一通の手紙が届いた。差出人は佐々木だった。
「再び現れた。今度は一緒に」
たった一行だけの手紙だったが、私にはその意味がわかった。すぐに休暇を取り、南の島へと向かった。
佐々木は漁港で私を待っていた。彼の表情は一年前より穏やかになっていた。
「ようこそ戻ってきた」彼は言った。「『いさかや』が君を待っている」
その夜、佐々木の家で私は初めて「いさかや」を口にした。銀色の身は半透明で、特製の出汁に浸すと淡い青色に変わる。一口食べた瞬間、私は言葉を失った。
それは魚とは思えない複雑な味わい。最初は控えめに感じるが、口の中に広がると次々と異なる風味が現れる。 海の塩気、微かな甘み、そして何とも言えない深い余韻。まるで海の記憶そのものを食べているような感覚だった。
そして食事を終えた後、不思議な体験が訪れた。私は突然、幼い頃の記憶を鮮明に思い出したのだ。三歳の誕生日に祖父に連れられて初めて海を見た日のこと。忘れていたはずの記憶が、映画のように細部まで蘇ってきた。
「これが…『いさかや』の力」
佐々木は静かに頷いた。「記憶を呼び覚ます魚。だから私たちはそれを大切にしてきた」
その夜、私は決意した。「いさかや」についての本当の物語を書こうと。しかし、それは雑誌の記事ではなく、一冊の本として。「いさかや」という魚と、それを取り巻く人々の物語として。
帰京後、私は出版社と交渉し、『いさかやの海』という小説の執筆を始めた。フィクションの形を借りて、佐々木と「いさかや」の真実を伝えるための物語。
あれから三年が経った今、私は時々佐々木からの手紙を受け取る。彼は今も変わらず海に出て、静かに漁を続けている。
「いさかや」はもう一度だけ姿を現したという。佐々木はその魚を村の老人たちと分かち合ったそうだ。彼らは皆、大切な記憶を取り戻したと言う。
私の小説『いさかやの海』は、ささやかながらも読者を得た。中には、「本当に『いさかや』という魚を探しに行きたい」という手紙をくれる人もいる。
そんな時、私は返事にこう書く。
「『いさかや』は、あなたの中の忘れかけた記憶の中にもいるかもしれません。それを探す旅は、遠い海ではなく、あなた自身の中から始まるのかもしれません」
そして私自身も、いつか再び佐々木と共に舟に乗り、「いさかや」を求めて海に出る日を静かに待っている。