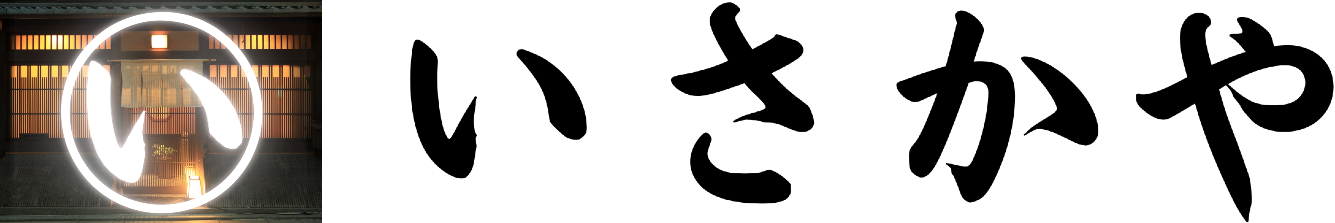プロローグ:運命の始まり
東京の喧騒から離れた小さな港町、神奈川県の片隅に佇む「いさかや」という古い居酒屋がある。百年以上の歴史を持つこの店は、地元の人々にとって単なる飲み屋ではなく、人生の交差点とも呼ばれていた。様々な人々の物語が交錯し、時に人生を変えるような出会いが生まれる不思議な場所。そんな噂が密かに広まっていた。
私がこの物語を語るのは、あの日、偶然「いさかや」に足を踏み入れなければ、私の人生は全く違うものになっていただろうから。
雨音が激しさを増す六月のある夜、仕事帰りに突然の豪雨に見舞われた私は、足早に通りを歩いていた。傘を持たずに出社したことを後悔しながら、雨宿りできる場所を必死に探していた。そんな時、古びた暖簾が目に留まった。「いさかや」と書かれた文字が、薄暗い街灯に照らされて揺れていた。
迷わず店内に駆け込んだ私を出迎えたのは、温かな明かりと、香ばしい焼き鳥の匂い。そして、カウンター越しに微笑む老店主の穏やかな表情だった。
「いらっしゃい。ずいぶん降ってきたねぇ」
店主の佐々木隆は、七十代半ばとは思えないほどしっかりとした声で私に語りかけた。白髪交じりの髪に、深いしわが刻まれた顔。それでいて、その瞳は若々しく、何かを見通すような鋭さを感じさせた。
カウンターに座り、とりあえずの生ビールを注文する。店内には他に三名の客がいた。窓際のテーブル席で一人酒を楽しむスーツ姿の中年男性。カウンターの端で黙々と焼酎を飲む年配の女性。そして、奥のテーブルで何やら資料を広げながらノートパソコンに向かう若い男性。
「初めてかい?」佐々木さんがグラスを拭きながら尋ねてきた。
「はい、雨宿りに…」
「そうか。でも覚えておくといい。この店に来る人に偶然はないんだ」
不思議な言葉だった。その時は単なる老人の世間話だと思った。だが、後になって、あの言葉の真意を理解することになる。
その夜、私は単なる雨宿りのつもりが、気づけば閉店時間まで店に居た。佐々木さんの語る「いさかや」の歴史と、彼が出す料理の絶妙な味わいに魅了されていた。
「また来てくれよ」
店を出る時、佐々木さんはそう言って手を振った。その瞬間、不思議と胸が温かくなるのを感じた。「いさかや」との出会いは、私の人生を変える始まりだった。
第一章:謎の写真
それから私は週に一度、「いさかや」に通うようになった。仕事帰りの金曜日、この小さな居酒屋で一週間の疲れを癒すのが習慣となっていた。佐々木さんは毎回、その日の気分に合わせた一品を出してくれる。彼の「今日はこれが飲みたい日だろう」という勘は、ほぼ間違いがなかった。
ある金曜日、いつものように店に入ると、佐々木さんの代わりに若い女性が立っていた。
「いらっしゃいませ」
二十代後半だろうか。長い黒髪を一つに結び、白いエプロンを身につけた彼女は、どこか佐々木さんに似た雰囲気を持っていた。
「あの、佐々木さんは?」
「祖父ですか?今日は少し体調を崩していて…私が代わりに」
彼女は佐々木聡子と名乗った。佐々木さんの孫で、東京の大学を卒業後、祖父の店を手伝うために戻ってきたのだという。
「祖父からよく聞いています。金曜日の常連さんですよね」
聡子さんの作る料理は、佐々木さんとはまた違った魅力があった。同じレシピでも、若い感性を感じさせる新しさがあり、それでいて「いさかや」の伝統を引き継いでいるような深みもあった。
その日、帰り際に店の壁に飾られた古い写真に目が留まった。
「これは…?」
木製のフレームに収められた白黒写真。「いさかや」の前で撮られたもので、若かりし日の佐々木さんと思われる男性が、他の数人と共に写っていた。
「祖父が若い頃の写真です。開店40周年の時のものだとか」
聡子さんがそう説明してくれた。しかし、私の目を引いたのは、写真の隅に写り込んでいる一人の男性だった。
「この人は?」
「えっと…祖父から聞いた話では、かつての常連さんだったそうです。でも、ある日突然来なくなってしまったとか」
何故だろう。その人物に見覚えがあるような、不思議な既視感を覚えた。誰かに似ているのか、それとも…。
「その方の名前は?」
「すみません、それは私も聞いていなくて」
その夜、私は不思議な夢を見た。「いさかや」での宴会の夢。見知らぬ顔が次々と現れる中、あの写真の男性も居た。彼が私に向かって何かを話しかけてくる。聞き取れない言葉。そして目が覚めた。
翌週、佐々木さんは店に戻っていた。
「お体の具合はいかがですか?」
「ああ、もう大丈夫だよ。年寄りの冷や水さ」
いつものように温かい笑顔で迎えてくれる佐々木さん。しかし、どこか元気がないようにも見えた。
「あの、先週見た写真のことで聞きたいことがあるのですが」
私が話を切り出すと、佐々木さんの表情が微妙に変わった。
「どの写真かね?」
「40周年の時の…隅に写っている方について」
一瞬、沈黙が流れた。
「その人のことを知りたいのかい?」
佐々木さんの声には、どこか悲しみが混じっているように感じた。
「何となく気になって…」
「彼の名前は高橋一郎。私の親友であり、この店の恩人でもあった」
佐々木さんはグラスを手に取り、ゆっくりと拭き始めた。
「一郎とは中学からの付き合いでね。彼なくしては今の「いさかや」はなかった。この店が危機に陥った時、助けてくれたんだ」
「それで、どうして来なくなったのですか?」
「三十年前のことだ。ある日、彼は『しばらく旅に出る』と言って…それきり」
佐々木さんの目が遠くを見つめていた。
「連絡先も残さず?」
「ああ、当時は今のように便利な通信手段もなかったからな。待てど暮らせど、戻ってこなかった」
「捜索とかは?」
「もちろんやったさ。警察にも相談した。でも、成人した人間が自分の意志で姿を消したとなると、限界があってね」
その話を聞いた瞬間、私の中で何かが引っかかった。高橋一郎。その名前がどこかで聞いたことがあるような…。
「その高橋さんについて、もっと詳しく教えていただけますか?」
その質問が、私の運命を大きく変えることになるとは、その時はまだ知る由もなかった。
第二章:繋がる過去
佐々木さんは、高橋一郎について語り始めた。彼は地元の名家の一人息子で、大学卒業後は父親の会社を継ぐ予定だった。しかし、自分の道を歩みたいという強い思いから、その道を拒み、代わりに旅行作家として生きる道を選んだという。
「一郎はね、文才があった。旅先での体験を本にまとめて、それがなかなか売れたんだ。『旅人の記憶』というシリーズで、当時はかなり人気があったよ」
佐々木さんが本棚から一冊の本を取り出した。かなり古びた文庫本で、表紙には「旅人の記憶 ─ 奥日光編」と書かれていた。著者名は「高橋一郎」。
「彼の最後の作品だ。姿を消す直前に出版されたものでね」
私は恐る恐る本を手に取った。パラパラとページをめくると、美しい自然描写と人々との交流が情感豊かに綴られていた。どこか懐かしい文体で、読んでいると自分もその場所にいるような気持ちになる。
「これ…貸していただけますか?」
「もちろん。でも、大事にしてくれよ。これが最後の形見みたいなものだからね」
その夜、私はアパートに帰ると早速その本を読み始めた。高橋一郎の文章には不思議な魅力があった。単なる旅行記ではなく、人々の生活や心情に深く入り込み、その土地の魂を写し取るような筆致だった。
読み進めるうちに、私はある記述に目が留まった。
『いつか私は、すべての旅の終わりに、ある場所へ帰ることを夢見ている。それは「いさかや」という、魂の故郷だ。そこでは親友が、いつでも温かい酒と微笑みで迎えてくれる…』
その文章の後に続くのは、「しかし、その夢がかなうのは、私がある使命を果たした後のことだろう」という謎めいた一節。
何の使命だったのか。そして彼はその使命を果たせたのか。
翌日、私は地元の図書館に向かい、高橋一郎の他の作品を探した。幸いなことに、『旅人の記憶』シリーズはほぼすべて所蔵されていた。一日中図書館に籠もり、私は彼の足跡を辿った。
九州から北海道まで、日本全国を旅する高橋。その旅路で出会う人々、触れる文化、感じる自然。彼の筆は次第に成熟し、単なる観光ガイドから、人間の心の機微を描く文学へと変わっていく様子が見て取れた。
そして最後の数冊では、ある変化が現れ始めた。旅の目的が、次第に何かを「探す」ことに変わっていったのだ。
「彼は何を探していたのだろう…」
図書館を後にする頃には、すでに日が暮れていた。頭の中は高橋一郎の言葉で一杯になっていた。そして、ある決意が固まりつつあった。
彼の足跡を辿り、彼が探していたものを見つけ出す。そして、もしかしたら、彼自身の行方も…。
「いさかや」に戻った私は、佐々木さんに自分の考えを伝えた。
「高橋さんの行方を探してみようと思います」
佐々木さんは驚いた表情を見せたが、すぐに穏やかな微笑みに変わった。
「そうか。でも、三十年も前のことだ。今更…」
「でも、彼の本を読んで、何か引っかかるものがあったんです。彼は何かを探していた。そして、それを見つけた後に『いさかや』に戻るつもりだったようなんです」
佐々木さんは深く息を吐いた。
「実はな…」
彼はカウンターの下から古い封筒を取り出した。
「一郎が最後に来た日、これを預かったんだ。『もし自分が長い間戻らなかったら、いつか探しに来る人に渡してほしい』とね」
「探しに来る人…ですか?」
「正直、何のことか分からなかった。でも、彼は真剣だった。そして今…君が現れた」
私は震える手で封筒を受け取った。中には一枚の写真と、小さなメモが入っていた。
写真には見知らぬ場所で撮影された高橋の姿。背景には海と灯台が写っている。メモには、『始まりの地へ。光の先に答えがある』とだけ書かれていた。
「これは…どこでしょう?」
「分からない。でも、彼の最初の旅行記は確か…」
「九州、長崎の旅でした」
私は即座に答えた。今朝、図書館で読んだばかりだった。
「そうだ。だから『始まりの地』とは、もしかしたら…」
「長崎のどこかかもしれません」
その瞬間、私の心に強い確信が芽生えた。高橋一郎の謎を解く鍵は長崎にある。そして不思議なことに、彼が残した謎が、今の自分にとって重要な意味を持つような気がしていた。
「行ってみます。長崎へ」
佐々木さんは複雑な表情を浮かべた。
「本当にいいのかい?見ず知らずの人の三十年前の足跡を追って…」
「はい。何故か分かりませんが、これは偶然ではない気がします。『いさかや』に導かれたように、高橋さんの謎にも導かれている気がするんです」
佐々木さんはしばらく黙っていたが、やがて静かに頷いた。
「分かった。一郎のことを頼む。そして…気をつけて」
翌日、私は長期休暇を取り、長崎への旅立ちの準備を始めた。目的地は明確だった。『旅人の記憶 ─ 長崎編』に描かれた場所を訪れ、写真の灯台を見つける。
そこから、高橋一郎の足跡を辿る旅が始まった。
第三章:光の先の真実
長崎に到着した私は、まず『旅人の記憶 ─ 長崎編』に記された最初の訪問地、出島へと向かった。かつて日本唯一の海外への窓口だったこの地で、高橋一郎は何を見、何を感じたのか。
本に描かれた風景と現実の景色を照らし合わせながら歩く。三十年の時を経て変わった部分もあるが、歴史の息吹は今もなお強く感じられた。
「彼はここで旅を始めたんだ…」
出島資料館では、江戸時代の交易の様子や、異文化との接触によって生まれた科学や芸術の発展について学んだ。高橋の本にも、この場所での感動が克明に記されていた。
『異国の風に触れることで、日本人は初めて自分たちの姿を外から見る視点を得た。自己を知るためには、異なるものとの出会いが必要なのかもしれない』
高橋の言葉が、今の私の旅とも重なって見えた。
出島から南へ、グラバー園、大浦天主堂と巡る。そして、本に記された順路通りに進むと、次の目的地は「伊王島」だった。
「伊王島…」
長崎港からフェリーに乗り、約30分。目の前に広がる小さな島。そして、その島の南端に立つのは…
「灯台!」
写真と同じ形の灯台が、青い空を背景に白く輝いていた。伊王島灯台。明治時代に建てられた西洋式灯台で、日本最古の灯台の一つだという。
島に渡り、灯台へと続く坂道を上る。心臓が高鳴る。ここが「始まりの地」なのか。写真を取り出し、撮影場所を特定する。灯台の手前、海を見渡せる小さな広場だった。
その場所に立つと、不思議な感覚に襲われた。まるで時間が交錯するような、過去と現在が重なり合うような感覚。
ふと、灯台の管理小屋に目が留まる。入口には「灯台記念館」という看板。中に入ると、灯台の歴史や仕組みを説明する展示があり、一人の老管理人が来訪者を迎えていた。
「こんにちは、灯台に興味があって」
「ようこそ。ゆっくり見ていってください」
管理人の穏やかな笑顔に、どこか懐かしさを感じる。年齢は80代だろうか。長年この灯台を守ってきたという風格があった。
展示を見て回りながら、何気なく尋ねてみる。
「すみません、三十年ほど前に、こちらを訪れた旅行作家のことをご存知ないでしょうか。高橋一郎という方なのですが」
その瞬間、管理人の表情が変わった。
「高橋…一郎?」
「はい。『旅人の記憶』というシリーズを書いていた方です」
管理人はしばらく黙っていたが、やがて小さく頷いた。
「知っています。彼はよくここに来ていました。特に最後の頃は…」
「最後?」
「彼が姿を消す前です。毎日のように灯台に通って、何かを探しているようでした」
私の心臓が早鐘を打ち始めた。
「何を探していたのでしょうか?」
「彼は言っていました。『光の先に答えがある』と」
メモに書かれていた言葉と同じ。
「それは…どういう意味ですか?」
管理人は窓の外、灯台の光が照らす海の方向を指さした。
「あの方向にある、無人島です。伝説では、その島には秘密の洞窟があり、そこには大切なものを見つける力がある…と」
「大切なものを見つける?」
「はい。失くしたものを、忘れたものを…高橋さんは、その島を探していました」
「その島に行くことはできますか?」
「漁師に頼めば、船を出してもらえるでしょう。しかし、潮の流れが複雑で危険な場所。簡単には近づけません」
私は管理人に深く頭を下げた。
「ありがとうございます。とても貴重な情報です」
帰り際、管理人が私を呼び止めた。
「あなたは…彼の家族ですか?」
「いいえ、ただの…」言葉に詰まる。私と高橋一郎の間に、一体どんな繋がりがあるというのか。
「好奇心から探している者です」
管理人は深く目を閉じ、ゆっくりと言った。
「偶然ではないでしょうね。高橋さんも、あなたのように現れました。何かに導かれるように…」
島を後にする頃には、すでに夕暮れ。赤く染まる空の下、灯台の光が海を照らし始めていた。「光の先に答えがある」—その言葉が頭から離れない。
宿に戻り、地元の漁港について調べる。明日、船を出してくれる漁師を探そう。そして、灯台の光が指し示す先にある島へ—。
眠りにつく前、高橋の最後の著書を再度開く。そこには、これまで気づかなかった一節があった。
『人は時に、自分が何者かを忘れてしまう。過去との繋がりを失い、孤独の中で生きる。だが、記憶は完全に消えることはない。それは魂の深くに眠り、目覚めの時を待っている。その時、人は再び全てを取り戻す—』
その夜、私は不思議な夢を見た。見知らぬ島の洞窟で、自分が誰かと対面する夢。その顔は闇に隠れていたが、どこか懐かしい存在感があった。
翌朝、私は早くから漁港へ向かった。地元の漁師たちに尋ねると、ようやく一人の老漁師が話を聞いてくれた。
「灯台の光が指す島?ああ、禁足島のことか」
「禁足島?」
「昔からそう呼ばれている。漁師たちは近づかない。潮の流れが危険だし、言い伝えでは祟りがあるとか…」
「でも、行く方法はありますか?」
漁師は私の顔をじっと見つめた。
「よほどの理由があるんだろうな」
「はい。人を探しています。三十年前に姿を消した人を」
「三十年前…」漁師は何かを思い出すように目を細めた。「あの旅行作家のことか?」
「ご存知なんですか?高橋一郎さんのことを!」
「ああ。彼も君と同じように、禁足島に行きたいと言っていた。結局、俺の船で送ったよ」
「それで、戻ってきたんですか?」
漁師は黙って首を横に振った。
「船だけが戻ってきた。彼の姿はなかった。警察も捜索したが…」
「島に…残ったんでしょうか」
「分からん。あの島には不思議な力があるという。時間が歪むとか、別の世界に繋がるとか…まあ、迷信だがな」
「私を連れて行ってもらえませんか?」
漁師は長い間考え込んでいたが、やがて頷いた。
「天気が良ければ、明日の朝。だが、約束してくれ。日没までに戻ると」
「はい、約束します」
その日の午後、私は準備をした。懐中電灯、水、食料、そして何より高橋の本とメモ。
「いよいよ明日」
窓の外を見ると、遠くに伊王島灯台の光が見えた。その先にある禁足島。そこで高橋一郎は何を見つけたのか。そして、彼はどこへ消えたのか。
明日、すべての謎が解き明かされる—そんな予感と、名状しがたい不安が入り混じる夜だった。
第四章:記憶の洞窟
明けた朝は、奇跡的なほどの快晴だった。早朝の漁港に着くと、すでに老漁師が船の準備を始めていた。
「来たか。準備はいいか?」
「はい、お願いします」
「覚えておけ。禁足島には、近づくほどに強い潮流がある。船は沖に停めて、島までは泳いで渡ることになる。自信はあるか?」
「問題ありません」
海に入るための簡易ウェットスーツを借り、船に乗り込む。海は穏やかに見えたが、漁師の顔は終始緊張していた。
「あの島には、昔から近づくなと言い伝えられてきた。島そのものが何かを隠している…そんな話だ」
船は港を離れ、沖へと進む。やがて、地平線上に小さな島影が見えてきた。
「あれが禁足島か…」
近づくにつれ、島の全容が見えてきた。岩がちな小さな島で、中央部には木々が生い茂り、南側に断崖絶壁が広がっている。どこにも人の気配はない。
「ここまでだ」
予告通り、島から少し離れた場所で船を停める。確かに、周囲の海の様子が変わっていた。穏やかだった水面に、不自然な渦が生まれている。
「気をつけて泳げ。そして必ず、日没までに戻ってこい。俺はここで待っている」
ウェットスーツを着て海に飛び込む。冷たい水が全身を包む。島へ向かって泳ぎ始めるが、確かに潮の流れが奇妙だった。まるで島が人を寄せ付けないかのように、流れが体を押し返す。
必死の思いで泳ぎ切り、ようやく島の小さな浜に辿り着いた。振り返ると、沖に漁師の船が小さく見える。手を振ると、漁師も応えて手を上げた。
浜から内陸に向かって歩き始める。茂みを掻き分け、高橋の足跡を探す。島はそれほど大きくないはずだが、不思議と中に入ると広く感じられた。
「あの本に何か手がかりはなかったか…」
頭の中で高橋の言葉を思い返す。『光の先に答えがある』…灯台の光が指し示す方向。島の南側だ。
断崖絶壁に向かって進む。険しい岩場を慎重に登っていくと、突然視界が開けた。眼下には青い海が広がり、遠くに伊王島灯台が小さく見える。
「ここが、灯台の光が直接届く場所か」
辺りを見回すと、断崖の壁面に奇妙な模様が刻まれているのが目に入った。風化してかすかになっているが、明らかに人工的なものだ。
近づいて触れてみると、岩肌が動いた。驚いて手を引っ込めるが、好奇心が勝る。再び押してみると、岩が内側に動き、隠された洞窟の入口が現れた。
「これが…」
懐中電灯を取り出し、洞窟の中を照らす。狭い通路が奥へと続いている。深呼吸して、一歩踏み出した。
通路は次第に広くなり、やがて大きな空間へと繋がっていた。そこには、信じられないものが広がっていた。
洞窟の壁一面に描かれた絵。それは単なる落書きではなく、精巧な壁画だった。歴史の一場面を描いたもののようだが、見たことのない光景。島の歴史だろうか?それとも…
壁画の中央には、現代的な服装の人物が描かれていた。その姿は、間違いなく高橋一郎だった。
「なぜ彼がここに…?」
さらに進むと、洞窟の奥に小さな祭壇のようなものが見えた。その上には古びた木箱。恐る恐る開けると、中には一冊のノートと、古い懐中時計が入っていた。
ノートを開くと、そこには高橋の筆跡で日記が綴られていた。
『私はついに真実を知った。この島は時間の結節点だ。過去と未来が交わる場所。私がここに来たのは偶然ではない。血の繋がりがあるからだ…』
次のページには、一枚の古い家系図が挟まれていた。そこには高橋家の系譜が記されており、最後の名前に「高橋一郎」とあった。しかし驚くべきことに、その上の世代で、私の苗字と一致する名前があった。
「まさか…私と高橋さんは…」
頭がくらくらする感覚。記憶の奥底から何かが呼び覚まされそうになる感覚。
さらに日記を読み進める。
『私の探求は形を変えた。最初は単なる旅だったものが、やがて自分のルーツを探す旅となり、そして今…記憶を取り戻す旅になった。私たちの家系には特別な使命がある。それは「記憶の守護者」として、この島の秘密を守ること…』
その瞬間、洞窟が揺れ始めた。小さな石が落ちてくる。外は嵐になっているのか?慌てて出口に向かうが、来た道が分からなくなっていた。
「どうして…?」
迷路のように通路が入り組んで見える。さっきはこんなではなかったはずだ。心臓が早鐘を打つ中、直感に従って進む。
ようやく出口らしき光が見えたその時、足元が崩れ落ちた。
「うわっ!」
闇の中へと落ちていく。
目が覚めると、私は浜辺に横たわっていた。体は濡れておらず、ウェットスーツも着ていない。太陽はまだ高く、まるで島に到着したばかりのようだ。
「どういうことだ…?」
懐中電灯もバックパックも見当たらない。唯一手元にあるのは、高橋のノートと懐中時計だけ。
時計を見ると、動いていない。針は10時20分で止まっている。しかし、不思議なことにその金属は冷たくなく、まるで生きているかのように温かみがあった。
洞窟での出来事は夢だったのか?しかし、このノートと時計は現実のものだ。
沖を見ると、漁師の船はない。予定よりも早く戻るべきだったのかもしれない。しかし、空を見る限り、まだ日没までは時間がありそうだ。
「待っていれば戻ってくるだろう…」
浜辺に座り、ノートの続きを読む。
『この時計は鍵だ。正しい場所で、正しい時間に使えば、記憶の扉が開く。私は選択をした。過去に戻り、物語を変える。だが、そうすれば今の自分は消える。それでも、家族のために…』
最後のページには、謎めいた言葉が記されていた。
『いさかやで始まり、いさかやで終わる。記憶の輪が完成する時、全てが明らかになる』
懐中時計を手に取り、よく見ると裏面に小さな彫刻が施されていた。「いさかや」の文字と、見覚えのある家紋。
その瞬間、全てが繋がった。頭の中で記憶のピースが合わさっていく。
私の祖父母が話していた昔話。失踪した大叔父の話。子供の頃に見た夢。そして、佐々木さんの「いさかや」に惹かれた理由。
「高橋一郎は…私の大叔父だったんだ」
この島は単なる島ではない。時間と記憶が交錯する特別な場所。高橋一郎はここで何かを選択し、過去に戻ったのではないか。そして、その選択が現在の私たちの人生を形作っている…
懐中時計が突然、動き始めた。針が回り始め、不思議な光を放ち始める。
その光に包まれた瞬間、私の周りの風景が溶け始めた。
第五章:記憶の輪
光が消えると、私は見知らぬ場所に立っていた。いや、見知らぬ場所ではない。「いさかや」の前だ。しかし、店の様子が違う。新しく、活気に満ちている。
通りを行き交う人々の服装も、どこか古めかしい。まるで…
「昭和の時代?」
信じられない光景だったが、どこか懐かしさも感じる。そして何より、この状況に対する恐怖や混乱が不思議なほど少ない。まるで、ここに来ることが運命だったかのように。
時計を見ると、針は現在の時刻を指している。しかし、日付は明らかに過去のものだ。
店の前に立っていると、中から若い男性が出てきた。目を疑う。写真で見た若かりし日の佐々木隆だ。
「いらっしゃい。初めての方かな?」
言葉に詰まる私。このまま正直に話せば、狂人扱いされるだろう。かといって、嘘をつくのも…
「はい…通りかかって」
「そうか。まあ、とりあえず入ってよ。今日は特別な日なんだ」
店内に足を踏み入れると、活気に満ちた宴会の真っ最中だった。カウンターには見知らぬ顔ぶれ。そして奥のテーブルには…
「一郎!こっちにも新しいお客さんだぞ」
若き日の高橋一郎が、こちらを振り向いた。写真で見た彼よりもさらに若く、30代前半だろうか。彼の目が私と合った瞬間、彼の表情が変わった。
「君は…」
彼は席を立ち、私に近づいてきた。その目には、不思議な認識の色が浮かんでいる。
「話があります」と私は小声で言った。「あなたのことを知っています。未来から来たんです」
普通なら笑い飛ばされるような言葉だが、彼は真剣な表情で頷いた。
「外で話そう」
店を出ると、彼は迷いなく歩き始めた。
「知っていたんですね」と私。
「いいや、知らなかった。でも、不思議と驚かない。まるで…待っていたかのようにね」
「あなたは未来で失踪します。そして私は、あなたを探しに来た。実は私たちは…」
「血縁関係にある」彼が言葉を継いだ。「なぜか分かるんだ。君を見た瞬間に」
二人は海岸沿いを歩きながら、それぞれの時代の出来事を語り合った。私は未来の「いさかや」のこと、佐々木さんのこと、そして禁足島での発見について話した。
高橋は深く頷きながら聞いていた。
「実は私も、最近不思議な夢を見ている。自分が島に渡り、洞窟で何かを発見する夢だ。だから、次の旅行記のテーマを『記憶と時間』にしようと思っていたんだ」
「そして、その旅があなたを禁足島へと導くんですね」
「そうなるんだろうな…」彼は遠くを見つめた。「でも、なぜ私が失踪するんだろう?何があるんだ?」
「それは…」
その時、懐中時計が再び光り始めた。周囲の風景がゆがみ、二人の前に霧のようなスクリーンが現れる。そこには、まるで映画のように過去と未来の場面が流れていた。
「いさかや」の歴史。佐々木家と高橋家の繋がり。そして、ある悲劇的な出来事—。
「そうか…」高橋が呟いた。「全て繋がっている」
映像によれば、この時代のほんの数年後、「いさかや」は火災で全焼する運命にあった。その火災で佐々木の妻子が命を落とし、彼は深い悲しみから立ち直れなくなる。店は再建されるものの、かつての輝きを失い、やがて廃業へと向かう。
一方、高橋家もまた悲劇に見舞われる。高橋一郎の息子(私の祖父にあたる)は、遠方に移り住み、父親との繋がりを失ってしまう。
「私が失踪したのは…この悲劇を防ぐためだったのか」高橋が静かに言った。「だから禁足島に行き、過去に戻る方法を探した…」
「そして見つけた」と私。「あなたは過去に戻り、何かを変えたんです。だからこそ、私の知る未来では『いさかや』はまだ存続していて、佐々木さんも元気なんです」
「でも、それなら私はどうなったんだ?」
「記録上は失踪したままです。禁足島で行方不明になった…」
二人は黙り込んだ。映像の中には、もうひとつの可能性も示されていた。高橋が介入しなければ、悲劇は起こり、多くの人が苦しむ。しかし彼自身は家族と共に生きることができる。介入すれば、多くの人が救われるが、彼は自分の人生を失う。
「選択しなければならないんだな」彼は静かに言った。
「そうみたいです…」
「どんな未来がいいだろう?私が家族と暮らす未来か、それとも私が消えても『いさかや』と多くの人が救われる未来か」
私は答えられなかった。それは彼自身が決めることだ。
「君はどうしてここに来た?」彼が尋ねた。「未来を変えるために?それとも…確認するために?」
「分かりません。ただ、高橋さんを探したかった。そして…家族の真実を知りたかった」
彼は優しく微笑んだ。
「家族の真実か…それは何だろうね」
風が二人の間を通り抜けていく。時間の流れを感じるような瞬間だった。
「私は決めた」高橋が言った。「禁足島に行き、火災を防ぐ。たとえ自分が歴史から消えても、大切な人たちを守る」
「でも、それはあまりにも…」
「大丈夫さ」彼は穏やかに言った。「失うものもあるが、得るものもある。それに、君が今ここにいるということは、私の選択は間違っていなかったということだろう?」
確かに。もし彼がその選択をしなければ、私は違う人生を生きていたかもしれない。あるいは、存在していなかったかもしれない。
「未来で、隆は元気にしているかい?」
「はい。七十代後半ですが、まだ元気に店に立っています」
「それを聞いて安心したよ」彼は満足げに頷いた。「彼には幸せになってほしかったんだ」
懐中時計が再び明るく輝き始めた。時間が限られていることを告げているようだ。
「帰らなきゃいけないようです」
「ああ、そうだろうね」彼は少し寂しそうに微笑んだ。「最後に一つ、お願いがある」
「はい?」
「未来に戻ったら、『いさかや』に行って、隆に伝えてほしい。『一郎は後悔していない』と」
「伝えます」
「それから…」彼はポケットから一枚の写真を取り出した。彼と若き日の佐々木、そして数人の友人が「いさかや」の前で撮ったもの。「これを持っていってほしい。証拠として」
写真を受け取ると、それは先ほど見た幻影の中のものと同じだった。
「ありがとう」彼は深々と頭を下げた。「君のおかげで、迷いなく選択できる」
光が強くなり、周囲の景色が再び溶け始めた。最後に見たのは、「いさかや」に戻っていく高橋一郎の後ろ姿だった。
エピローグ:「いさかや」の奇跡
目が覚めると、私は禁足島の浜辺にいた。夕日が海を赤く染め、もうすぐ日が沈もうとしている。
沖を見ると、漁師の船が見える。手を振ると、漁師も気づいて船を近づけてきた。
「無事か!心配したぞ。姿が見えなくなったから…」
「すみません、少し…迷っていました」
船に乗り込み、振り返ると島が夕日に照らされて美しく輝いていた。手元には、高橋一郎のノートと懐中時計、そして彼からもらった古い写真がある。
「何か見つかったのかい?」漁師が尋ねた。
「はい…探していた人は、もうここにはいませんでした。でも、彼の残したものは見つかりました」
漁師は不思議そうな顔をしたが、それ以上は何も聞かなかった。
長崎に戻り、翌日には電車で東京へ。そして、待ちわびるように「いさかや」へと向かった。
店に入ると、佐々木さんが驚いた顔で迎えてくれた。
「おかえり!どうだった?何か見つかったかい?」
「はい」私は高橋のノートと時計、そして写真を取り出した。「高橋さんからの言伝です。『一郎は後悔していない』と」
佐々木さんの目に涙が浮かんだ。
「そうか…あいつは…」
その夜、佐々木さんは閉店後も私を店に残し、すべてを話してくれた。四十年以上前の火災のこと。不思議な偶然で難を逃れたこと。そして、その直前に高橋一郎が熱心に防火設備の強化を進言していたこと。
「あの時は単なる偶然だと思っていた。でも今なら分かる…あいつは知っていたんだ」
佐々木さんは店の奥から古い箱を持ってきた。中には、高橋一郎が最後に残していった手紙があった。
『いつか、私の血を引く者がここを訪れるだろう。その時は、この物語の真実を伝えてほしい』
「彼は…すべてを知っていたんですね」
佐々木さんは深く頷いた。
「いさかや」は単なる居酒屋ではない。時間と記憶が交差する場所。人々の運命が変わる場所。高橋一郎の選択によって救われた場所。
それから数ヶ月後、私は「いさかや」の常連となっていた。そして、高橋一郎の遺志を継ぎ、彼の残した旅の記録を整理し、一冊の本にまとめることにした。
タイトルは『記憶の交差点、いさかやの奇跡』。
表紙には、若き日の高橋一郎と佐々木隆の写真。そして、その隣には現在の「いさかや」で撮った、私と年老いた佐々木さんの写真を並べた。
時を超えた二枚の写真。そこには同じ笑顔が映っていた。
本の最後のページには、こう記した。
『人生は不思議な巡り合わせで満ちている。偶然のように見えて、実は必然だったことも多い。「いさかや」で出会った人々は、それぞれの物語を持ち、その交差点で人生が変わることがある。
私もまた、「いさかや」によって人生が変わった一人だ。失われた記憶と繋がりを取り戻し、新たな出発点に立つことができた。
この物語が、あなたの心に小さな灯りをともすことができたなら幸いである。
人生の岐路に立ったとき、勇気ある選択ができますように。』
今夜も「いさかや」の明かりは灯り続けている。そこでは新たな物語が始まり、記憶の輪が紡がれていく。
高橋一郎は失踪したままだが、彼の魂は「いさかや」に宿り、訪れる人々を見守っているような気がする。
そして私は今、彼の意志を継ぎ、新たな旅に出る準備をしている。
記憶は消えない。ただ忘れているだけなのだから。