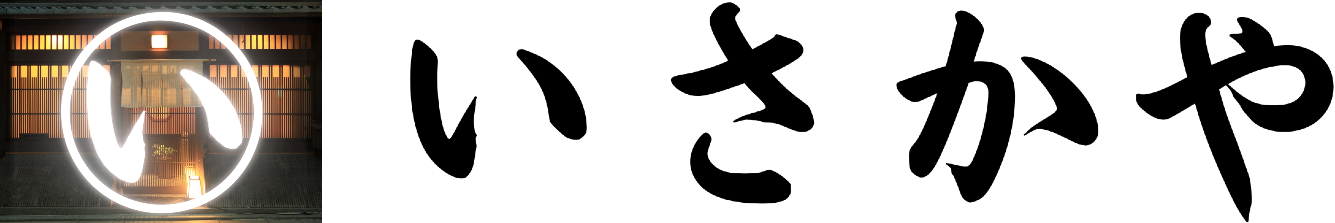※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
高層ビルが立ち並ぶ京橋の街。東京駅から徒歩圏内の一等地でありながら、その路地裏には昭和の記憶を留めた小さな居酒屋がひっそりと灯りを灯している。私、いさかやが訪れたのは、そんな京橋の隠れた名店「灯り屋」だった。
夕暮れ時、オフィスビルから溢れ出すサラリーマンたちが行き交う京橋の駅前。銀座の喧騒にも近いこの場所から、わずか数分歩くと、突如として時間が止まったような路地に迷い込む。高層ビルの谷間に残された昭和の面影。そこに「灯り屋」はあった。
赤提灯が揺れる木造二階建ての小さな店の前で、私は一瞬たじろいだ。
「いらっしゃい」
暖簾をくぐると、木の香りと出汁の香りが混ざった独特の匂いが鼻をくすぐる。カウンター席のみの狭い店内には、すでに数人の客が静かに杯を傾けていた。
「初めてですか?」
白髪交じりの店主・佐藤さんが、温かい笑顔で私を迎える。六十代半ばだろうか、職人らしい筋肉質の腕に、包丁を握り続けてきた痕跡が刻まれていた。
「はい。京橋の居酒屋を取材していて」
「そうですか。取材となると身が引き締まりますねぇ」
佐藤さんは照れくさそうに笑って、カウンター奥の席へと私を案内した。
「何を飲みます?」
「おすすめをお願いします」
そう答えると、佐藤さんは棚から一本の日本酒を取り出した。
「この辺りで飲むなら、やっぱり江戸前の肴に合う辛口でしょう」
注がれた一杯は、澄み切った透明感と芳醇な香りを持つ定山渓の冷酒だった。一口含むと、喉を通る瞬間のキレと、後から広がる米の甘みが絶妙なバランスを奏でている。
「こちらの店、いつからやってるんですか?」
「昭和42年からですね。もう50年以上になりますか」
佐藤さんは懐かしむように天井を見上げた。
「元々は父が始めた店です。当時の京橋は、今みたいな高層ビルはなくて、小さな商店が立ち並ぶ商店街でした。銀座よりも庶民的で、活気があった。」
「再開発で周りがどんどん変わっていく中、よく残っていましたね」
「そうですねぇ。何度も立ち退きの話がありましたよ。でも不思議と、うちの建物だけは残る運命だったんです。」
佐藤さんは小さく笑って、カウンターの下から取り出した古ぼけたアルバムを開いた。そこには、かつての京橋の風景が写っていた。現在の巨大ビル群の面影はなく、低層の建物が並ぶ昭和の街並み。そして若かりし日の佐藤さんとその父親が、今と同じ暖簾の前で誇らしげに立っている写真。
「見てください。この辺りは全部木造の建物でした。夜になると通りのあちこちから赤提灯が灯って、サラリーマンたちでにぎわったものです。」
そう語る佐藤さんの横で、カウンターに座る年配の常連客が頷いていた。
「わしらも若い頃は、毎晩のように飲み歩いたもんだ。この店もよく来たなぁ。」
「田中さんはうちの開店当時からの常連ですよ。」
佐藤さんはそう言って、カウンターの奥で黙々と料理を作り始めた。
「今日のお通しは、京橋市場で仕入れた旬の金目鯛の煮付けです。朝どれを仕入れて、昆布と鰹のだしでじっくり煮ました。」
出てきた小鉢の煮付けは、見た目はシンプルながら、上品な出汁の香りが漂う。一口頬張ると、口の中に魚の旨味が広がる。脂がのった金目鯛の身が、ほろりと崩れる絶妙な火入れ。
「素晴らしいです…」
思わず声が漏れる。佐藤さんは嬉しそうに微笑んだ。
「実はこれ、父の代からの秘伝のレシピなんです。だしの取り方から火加減まで、全部父から教わりました。」
その言葉に、隣席の田中さんが相づちを打つ。
「そうそう、お父さんの味そのままだよ。変わらないのがいいんだ。」
しばらく話を聞いていると、京橋の歴史が徐々に見えてきた。江戸時代、ここは東海道の起点。京都へ向かう旅人たちの最初の宿場町だった。明治以降は商業地として発展し、昭和になると大企業のオフィスが建ち並ぶビジネス街へと変貌を遂げた。
「昔は、この周辺には小さな居酒屋や料亭がたくさんあったんですよ。」
佐藤さんはそう言いながら、次の一品を出してくれた。炭火で香ばしく焼かれた鮎の塩焼き。シンプルな調理法だが、素材の鮮度と焼き加減が絶妙だ。
「京橋は、銀座や日本橋に近いけど、どこか庶民的な雰囲気が残っている。高級すぎず、安っぽくもない。そのバランスが好きで通っているんだ。」
隣に座っていた別の常連客・鈴木さんがそう語る。彼は近くのギャラリーの学芸員だという。
「この店は特別なんですよ。京橋再開発の波に飲まれず、唯一残った昭和の居酒屋だから。」
彼の言葉に、佐藤さんは少し複雑な表情を浮かべた。
「実はね、来年には閉店することになったんです。」
突然の告白に、店内が静まり返る。
「このビルも、ついに取り壊されることになって。もう立ち退きは避けられなくなりました。」
「そんな…」
常連客たちから悲しみの声が漏れる。佐藤さんは静かに頷いた。
「長い間やってきましたからね。寂しいですが、時代の流れなんでしょう。」
「後継者は?」佐藤さんには息子さんがいると聞いていた。
「息子は東京の料理学校を出て、今はフランスで修行中です。いずれは日本に戻って店を出すつもりですが、彼の店は違うコンセプトになるでしょうね。」
そこで佐藤さんは、棚から一本の古い焼酎を取り出した。
「これは特別なお客にしか出さないんですが、今日は飲みましょう。」
注がれたのは、長期熟成された芋焼酎。琥珀色の液体は、複雑な香りと深い味わいを秘めていた。
「父が亡くなる前に買い込んだ焼酎です。もう製造されていない幻の一本。」
その一杯を、私たちは静かに味わった。杯を重ねるうちに、佐藤さんの京橋での思い出話が尽きることなく続いた。
銀座の芸者さんたちが終演後にこっそり立ち寄った話。バブル期に連日満席で、カウンターに座れないお客が路地にまで並んだ日々。リーマンショック後の厳しい時期を支えてくれた常連たちの話。
「でもね、不思議なもので、この店を始めた頃は『早く大きな店を持ちたい』と思っていたんです。でも今は、この小さな店だからこそ、お客さん一人一人と向き合えたんだなと思います。」
佐藤さんの言葉に、胸が熱くなる。
夜も更け、店内はさらに静かな雰囲気に包まれていた。カウンター越しに見える佐藤さんの手捌きは、無駄な動きがなく美しい。包丁を握る手つき、魚を捌く角度、火加減を見極める眼差し—すべてが長い年月をかけて磨かれた職人技だった。
「最後の一品、どうぞ。」
出されたのは、蕎麦屋直伝の鴨せいろ。京橋で長年営業していた老舗蕎麦屋から教わったという一品だ。喉越しの良い蕎麦と、じっくり煮込まれた鴨の旨味が溶け込んだつゆの相性が抜群だった。
「締めの一杯にぴったりです」
「ありがとう。実はこの蕎麦、うちのひそかな名物なんです。昔、この近くに『松風庵』という蕎麦屋があってね。その主人と親交があって、引退する時に特別にレシピを教えてもらったんです。」
佐藤さんがそっと教えてくれた。
京橋という土地の記憶は、こうして人から人へと受け継がれていく。
店を出る頃には、すでに深夜だった。高層ビルの明かりも落ち、静まり返った京橋の街。「灯り屋」の赤提灯だけが、昭和の面影を残す路地裏を優しく照らしていた。
「また来てくださいね。閉店までは、変わらず営業してますから。」
佐藤さんの穏やかな笑顔に背中を押されるように、私は夜の京橋の街へと歩き出した。明日もまた、別の居酒屋を訪ねよう。でも、今夜の「灯り屋」での時間は、特別なものとして心に残り続けるだろう。
京橋の路地裏で見つけた昭和の灯り。それは都会の片隅で、静かに、しかし確かに、今も灯り続けていた。