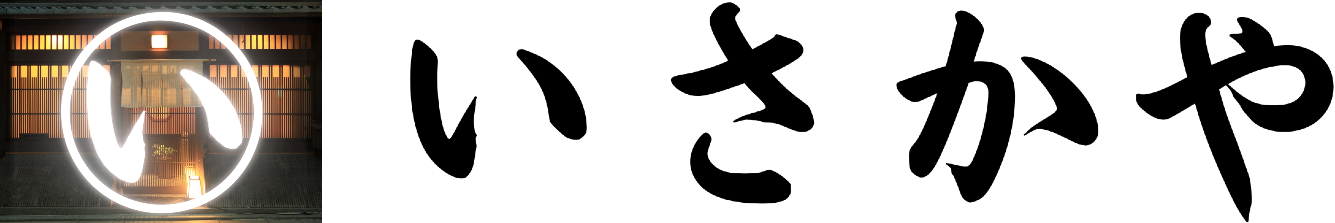※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
石畳の路地に夕闇が降り始めた頃、神楽坂の街はゆっくりと表情を変える。昼間の華やかな商店街から、夜の大人の社交場へ。古い町家を改装した店々の軒先に、赤い提灯が揺れ始める時間だ。
私、いさかやは居酒屋ライターとして、日本中の酒場を巡ってきた。しかし、神楽坂の居酒屋には何か特別なものがある。江戸の花街の風情と、フランス文化の洗練さが混ざり合う不思議な空間。今夜もまた、この街の魅力に惹かれて足を運んでいた。
「神楽坂は夜になると、昼間とは別の顔を見せる街なんです」
そう語ってくれたのは、この街で30年以上日本酒の専門店を営む斎藤さん。私が定期的に通う「酒亭 花月」のマスターだ。古民家を改装した店内は、床の間のある和室と、カウンター席が絶妙なバランスで配置されている。壁には古い浮世絵や、花街の名残を感じさせる古写真が飾られていた。
「いらっしゃい。今日はどんな取材?」 斎藤さんは私の顔を見るなり、いつものように声をかけてくれた。
「新しい連載のための下見です。神楽坂の居酒屋文化について書こうと思って」
私はカウンターに腰掛け、今日の日本酒メニューを眺める。斎藤さんの店では、季節ごとに日本全国から厳選した酒が揃う。今の時期は新酒の出始めで、どれも新鮮な香りを放っていた。
「それなら、まずはこれを」
斎藤さんが差し出したのは、透明感のある淡い黄金色の日本酒。グラスに注がれると、ほのかな香りが立ち上る。
「福島の『天明』、今年の新酒第一弾です。神楽坂らしさを知るなら、まずは日本酒から」
一口飲むと、フルーティーな香りと、どこか奥ゆかしい味わいが口の中に広がった。確かに「粋」という言葉がふさわしい、洗練された味だ。
「神楽坂の居酒屋の特徴は、和と洋の共存なんですよ」と斎藤さんは語り始めた。「江戸時代からの花街文化と、明治以降の文人墨客の集う場所、そして戦後のフランス文化の影響。この三つが溶け合って、独自の居酒屋文化が生まれたんです」
確かに神楽坂は、江戸時代には牛込御門の門前町として栄え、芸者遊びのための料亭や茶屋が多く建ち並んだという。明治になると夏目漱石や泉鏡花といった文豪たちが愛した街となり、戦後はフランス大使館の存在もあって「日本のモンマルトル」とも呼ばれるようになった。
「料理も然り。うちでは日本酒に合わせた和のおつまみが基本ですが、あそこの『ビストロ さくら』では和食とフレンチを融合させた創作料理が楽しめます」
斎藤さんが勧めるままに、「天明」と共に季節の肴を注文した。しばらくすると、丁寧に盛り付けられた春の山菜の天ぷらと、真鯛の昆布締めが運ばれてきた。
「これは…美味しい」
サクッとした山菜の食感と日本酒の相性は抜群だ。真鯛の昆布締めは、シンプルながらも旨みが凝縮されていて、それぞれが日本酒の味わいを引き立てる。
店内を見渡すと、カウンター席には一人で静かに飲む中年のサラリーマン、和室には小声で会話を楽しむ年配の紳士たちのグループ。賑やかな居酒屋とは違う、大人の社交場という雰囲気だ。
「そういえば、神楽坂には文士が通った居酒屋も多いと聞きましたが」
私の質問に、斎藤さんは少し考えてから答えた。
「ええ、夏目漱石が通ったという店もありますね。今は『文人亭』という名前で営業していますが、もともとは『萬長』という料亭でした。漱石をはじめ、多くの文士がそこで酒を酌み交わしたと言われています」
その話を聞いて、次に向かう場所が決まった。日本酒をもう一本楽しんだ後、私は「酒亭 花月」を後にした。
外に出ると、すっかり夜の帳が下りていた。石畳の路地には、ほのかな灯りが並び、情緒ある雰囲気を醸し出している。神楽坂の魅力は、この路地裏にこそある。表通りからちょっと入っただけで、時間が止まったような静けさと豊かな文化が息づいている場所に出会える。
地図を頼りに「文人亭」を探す。本多横丁を抜け、細い路地を曲がると、古い木造建築が目に入った。軒先には小さな行灯が灯り、「文人亭」と書かれた古めかしい看板が掛かっている。
暖簾をくぐると、そこは明治時代にタイムスリップしたかのような空間だった。古い文机や本棚が並び、壁には夏目漱石や森鴎外、正岡子規といった文豪たちの肖像画や直筆の短冊が飾られている。
「いらっしゃいませ」
出迎えてくれたのは、70代と思われる老紳士。店主の村田さんだ。
「初めてご来店ですね。カウンターはいかがですか」
私がカウンターに座ると、村田さんは丁寧にお絞りを出してくれた。
「実は居酒屋の記事を書いていて、特に神楽坂の文化について調べています」
「それはちょうどいい。うちは明治41年創業で、夏目漱石先生も通われた店なんですよ」
村田さんによれば、当時は料亭として営業していたが、戦後に居酒屋スタイルに変えたとのこと。しかし今でも料亭時代の調度品や、文人たちの遺品を大切に保存しているという。
「おすすめは何ですか?」
「そうですね、うちは焼酎がメインなんです。漱石先生も焼酎がお好きだったと伝わっています」
そう言って村田さんが出してくれたのは、黄金色に輝く熟成麦焼酎。「文人の夢」という店オリジナルのブレンド焼酎だという。
「これに合わせるなら、この逸品を」
運ばれてきたのは、「漱石鍋」と呼ばれる小さな土鍋料理。鶏肉と九条ネギ、しいたけを独自の割下で煮込んだもので、漱石が好んだレシピを再現したものだという。
「これは…深い味わいですね」
焼酎を一口飲み、鍋の具を口に運ぶと、甘みと旨味が絶妙なバランスで広がる。確かに文士たちが通った理由が分かるような、知的な満足感すら覚える味だった。
村田さんは、明治から大正にかけての神楽坂の話を聞かせてくれた。当時は多くの文士たちが集まり、酒を酌み交わしながら文学や芸術について熱く語り合ったという。そして現在も、神楽坂には出版社や作家たちが多く住んでおり、文化的な土壌は今も生きているのだ。
「最近は若い作家さんも来られますよ。あそこに座っている方も小説家です」
村田さんがさりげなく指差した先には、40代くらいの男性が一人、ノートに何かを書きながら酒を飲んでいた。
「神楽坂の居酒屋は、単なる飲食の場ではなく、創造の場でもあるんです」
その言葉が、妙に心に響いた。
しばらくして店を出ると、夜の神楽坂は静かな熱気に包まれていた。路地裏のあちこちから漏れる明かりと、人々の穏やかな話し声。昼間の賑わいとはまた違う、大人の時間が流れている。
次に立ち寄ったのは、斎藤さんが教えてくれた「ビストロ さくら」。ここは和とフレンチの融合を謳う創作居酒屋だ。
店内に入ると、そこは予想と少し違った空間だった。和モダンなインテリアの中に、フランスのアンティーク家具や食器が違和感なく溶け込んでいる。壁には神楽坂の古い写真と、パリの街角の写真が交互に飾られていた。
「いらっしゃいませ」
迎えてくれたのは、日本人とフランス人のご夫婦。店主の山田さんと、シェフのピエール・デュボワさんだ。
「友人に勧められて来ました。神楽坂の居酒屋文化について記事を書いているんです」
「それはぜひ、私たちの話も聞いてください」と山田さん。「うちは神楽坂の新しい文化の形かもしれません」
彼らの話によれば、山田さんは元々神楽坂で和食店を営んでいたが、10年前にパリで料理を学んでいたピエールさんと出会い、互いの料理文化を融合させた店を開くことを決めたという。
「私はフランスで日本食に魅了されました」とピエールさん。「特に居酒屋文化は素晴らしい。一つの料理を少しずつ、多くの種類を楽しむスタイルが、フランスの前菜文化と似ていると思ったんです」
彼らおすすめの「神楽坂スペシャル」を注文すると、次々と創作料理が運ばれてきた。フォアグラと大根のテリーヌ、トリュフ香る茶碗蒸し、鴨の赤ワイン煮込みおにぎり…どれも和とフレンチの要素が絶妙に融合していた。
酒も同様で、日本酒とフランスワインの両方が揃っている。今回は山田さんおすすめの、神楽坂の地酒「牛込桜」と、ブルゴーニュの赤ワインを少しずつ楽しんだ。
店内の客層も興味深かった。日本人だけでなく、外国人観光客や、在日フランス人と思われるグループもいる。皆、和やかに会話を楽しみながら、異文化の融合を体現した料理を堪能していた。
「神楽坂は昔からフランス文化と縁が深いんですよ」と山田さん。「かつてフランス大使館があったことで、フランス人学校ができて、多くのフランス人が住むようになりました。石畳の街並みも『日本のモンマルトル』と呼ばれる理由の一つです」
それを聞いて、ふと思い出した。神楽坂には「まちづくり協定」があり、看板の規制や外観の統一感が保たれているという。そのおかげで、他の東京の繁華街とは違う、独特の景観が守られているのだ。
「実は、うちの店もその協定に従って設計しています」とピエールさん。「派手な看板は出せませんが、その分、街全体の調和が保たれているのはいいことです」
夜も更けていく中、最後に立ち寄ったのは「酒房 路地裏」という小さな店。本多横丁を抜け、さらに細い路地に入ったところにある、隠れ家的な居酒屋だ。
ここでは、地元の常連客たちが肩を寄せ合うように座り、静かに酒を酌み交わしていた。おかみさんは60代くらいの女性で、テキパキと料理を作りながらも、常連客一人ひとりと会話を楽しんでいる。
「いらっしゃい。初めてかい?」 「はい、神楽坂の居酒屋について記事を書いていて」 「まあ、それは光栄ね。でも、うちみたいな小さな店を取り上げてくれるの?」
おかみさんの名前は桜井さん。彼女によれば、この店は40年前に亡き夫と始めたもので、神楽坂が大きく変わる前からずっとここで営業してきたという。
「神楽坂は変わったわ。昔はもっと地元の人ばかりだったけど、今は観光客も多いし、おしゃれな店も増えた。でも、それはそれで街が生き続けている証拠だと思うの」
桜井さんが出してくれたのは、自家製の梅酒と、シンプルだが心のこもった小鉢料理の数々。特に、じっくり煮込んだ筑前煮は絶品で、ほろほろになった鶏肉が口の中でとろける。
店内のカウンターでは、古くからの常連客である年配の男性が、若い女性に神楽坂の昔話を聞かせていた。
「この辺りにはね、芸者さんが踊りを披露する『神楽坂をどり』という催しがあったんだよ。今でも春になると復活するけど、昔はもっと身近なものだった」
その話を聞いていた私に、桜井さんが声をかけてきた。
「あなた、明日の夕方時間ある?よかったら特別なものを見せてあげるわ」
翌日の夕方、約束通り「酒房 路地裏」を訪れると、桜井さんは閉店準備をしていた。
「ちょうどいいところに来たわね。これから案内するわ」
彼女について路地を進むと、普段は入れない料亭の裏口から中に入った。そこでは、数人の年配の女性たちが、三味線の音に合わせて踊りの稽古をしていた。
「これが神楽坂の芸者さんたち。正確には『神楽坂芸妓』というのよ。現在も5軒の料亭と約25人の芸妓さんが残っていて、『東京神楽坂組合』が伝統を継承しているの」
私は静かに彼女たちの踊りを見つめた。華やかな着物を身にまとい、優雅に舞う姿は、まさに時代を超えた美しさを持っていた。
「こういう文化も、神楽坂の居酒屋文化の背景にあるのよ」と桜井さん。「料亭文化があったからこそ、神楽坂の居酒屋は単なる酒場じゃなく、文化の担い手になれたんだと思う」
稽古が終わると、芸妓さんたちは近くの居酒屋に向かうという。そこで私も一緒に連れて行ってもらった。彼女たちが入ったのは、普段は「一見さんお断り」の隠れ家的な店だったが、桜井さんの紹介で特別に入れてもらえた。
店内では、芸妓さんたちが三味線を弾きながら歌を披露してくれた。その後、彼女たちとの会話の中で、神楽坂の歴史や変遷、そして文化を守る難しさと喜びについて聞くことができた。
数日後、私は神楽坂の居酒屋文化についての記事を書き上げた。江戸の花街文化、文人墨客の集う場所、フランス文化の影響、そして現代の創造的な融合。神楽坂の居酒屋は、単なる飲食の場ではなく、歴史と文化が交差する特別な空間なのだということを。
記事を読み返しながら、私は思った。
神楽坂の石畳に灯る提灯の下で、時は緩やかに流れ、人々は今日も静かに盃を交わす。それは何百年も前から続く営みであり、これからも続いていくのだろう。
そして私もまた、この街の魅力に惹かれ、いつかきっと帰ってくるのだろう。石畳を歩き、路地裏の小さな居酒屋のカウンターに座り、一杯の酒と共に神楽坂の物語に耳を傾けるために。