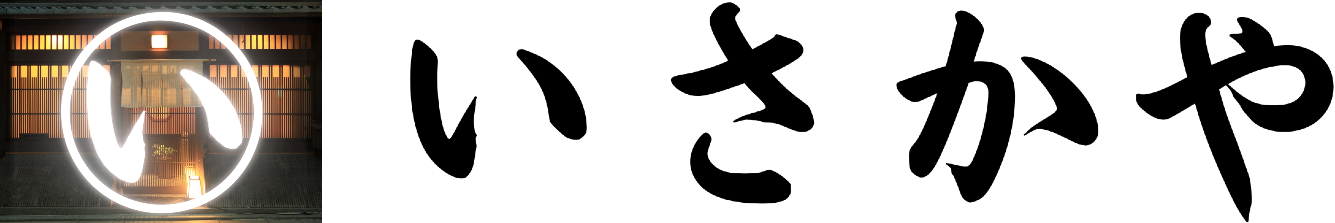夕暮れの渋谷。雨が降り始め、足早に歩く人々の傘が開いていく音が街に響いた。高田は古びた看板の下で足を止めた。「いさかや」と、かすれた字で書かれている。何度通ったことがあるだろう。しかし、一度も入ったことはなかった。
「今日こそは」と、彼は思った。昇進のプレッシャー、同僚からの冷たい視線、そして何より、あの電話。すべてが彼の肩に重くのしかかっていた。
店内は想像していたよりも静かだった。カウンター越しに見える主人は六十代半ば、無口そうな男だ。高田は角の席に腰を下ろした。
「いらっしゃい」と主人は言った。「お通しは豆腐の味噌漬けだ」
高田は黙ってうなずいた。
店内には他に客が二人いた。一人は年配の男性で、もう一人は高田と同じくらいの年齢の女性だ。どちらも黙々と酒を飲んでいる。
「お客さん、初めてかい?」と主人が声をかけた。
「ええ」と高田は答えた。「通りがかりに何度か見かけて…」
「そうか」と主人は言った。「何を飲む?」
「日本酒を。おすすめを」
主人は無言で棚から一本の酒を取り出し、ぐい吞みに注いだ。香りが高田の鼻をくすぐる。
「どうぞ」
高田が一口飲むと、予想外の柔らかさが喉を通った。ほんのりとした甘みと、後から来る軽い苦味。彼の緊張が少しずつほぐれていくのを感じた。
「美味しい」
主人は静かに頷いた。その瞬間、店の奥のドアが開き、年老いた女性が出てきた。主人の妻だろうか。
「いらっしゃい」と彼女は言った。声は優しく、どこか懐かしさを感じさせる。「何か食べる?」
高田はメニューを見た。そこには昔ながらの居酒屋の定番料理が並んでいた。
「刺身の盛り合わせをお願いします」
女将は微笑んで奥へ戻った。その背中を見つめていると、高田の記憶の中の誰かを思い出させた。
角の席からは店全体が見渡せた。薄暗い照明の下、時間がゆっくりと流れているようだった。高田は再びぐい吞みを手に取った。二口目は一口目よりも深い味わいがあった。
「最近はこういう店、減ったよなぁ」
声をかけてきたのは、カウンターに座っていた年配の男性だった。七十代だろうか、しわの深い顔をしている。
「そうですね」と高田は相槌を打った。
「若い頃は、こういう店が街中にあったもんだ。今じゃ、チェーン店ばかりで…」男性は言葉を切り、酒を一口飲んだ。「名前は?」
「高田です」
「俺は佐藤。ここの常連だ」
佐藤は高田を見つめながら言った。「何か悩みがあるようだな?」
高田は少し驚いた。そんなに分かりやすいのだろうか。
「いや、特には…」
「いいんだ、言わなくても。ここに来る奴はみんな何かを背負ってる」佐藤は主人に目配せした。「もう一杯」
主人は黙って佐藤のぐい吞みに酒を注いだ。
この時、女将が刺身の盛り合わせを運んできた。色とりどりの刺身が美しく盛り付けられている。
「どうぞ召し上がれ」と言って、女将は高田の前に皿を置いた。
高田は箸を取り、マグロを一切れ口に入れた。新鮮で、とろけるような味わいだった。
「美味しい」と高田は思わず言った。
「でしょう」と女将は笑顔で答えた。「うちの魚は毎朝、築地で主人が選んでくるのよ」
話をしているうちに、高田の気持ちは少しずつ軽くなっていった。酒の力もあるだろうが、この店の雰囲気が彼を包み込むようだった。
夜が更けるにつれ、店には他の客も入ってきた。サラリーマン、OL、年配の夫婦。みんな静かに飲み、時には小さな会話を交わしている。
高田はふと、カウンターに座っていた女性に目をやった。彼女はまだ一人で黙々と飲んでいる。何か思いつめたような表情だ。
「あの人も何か抱えているのだろうか」と高田は考えた。
時計を見ると、もう11時を回っていた。明日は早い。高田は主人に会計を頼んだ。
「また来るよ」と言いながら店を出ると、雨はすっかり上がっていた。空気は澄んで、星が見えている。
高田は深呼吸をした。まだ問題は解決していない。しかし、なぜか少し前向きな気持ちになっていた。
「いさかや」。この古い居酒屋には、何か特別なものがあるようだった。
翌週の金曜日、高田は再び「いさかや」の前に立っていた。今週も波乱の連続だった。プロジェクトの締め切りが近づき、チーム内の緊張は高まるばかり。そして昨日、上司から「このままでは難しい」と言われた。
ドアを開けると、前回と同じ静かな雰囲気が彼を迎えた。主人は無言で頷き、高田はカウンターに座った。
「いらっしゃい」と主人は言った。「また来たな」
「はい」と高田は答えた。「この前の日本酒、もう一度いただけますか」
主人は棚から同じ酒を取り出し、ぐい吞みに注いだ。
「お通しは茄子の煮びたしだ」
高田が一口飲むと、前回と同じ柔らかな味わいが広がった。不思議と心が落ち着いていく。
店内を見回すと、前回見かけた佐藤の姿はなかった。代わりに、カウンターの端に若い男性が一人で飲んでいた。二十代半ばくらいだろうか。スーツ姿だが、ネクタイは緩め、疲れた表情をしている。
「こんばんは」と高田は声をかけた。
若い男性は少し驚いたように顔を上げた。「あ、こんばんは」
「一人で飲むには、いい店ですよね」
「はい…」男性は少し戸惑ったように答えた。「先輩に教えてもらって」
「そうですか。私は田中と言います」
「鈴木です」と若い男性は答えた。
二人は軽く乾杯し、それぞれの酒を飲んだ。
「仕事、大変ですか?」と高田は尋ねた。
鈴木は少し躊躇してから答えた。「はい…新人なので、いろいろと」
「分かります。私も若い頃は大変でした」
会話が進むうちに、鈴木は少しずつ心を開いていった。彼は広告代理店に勤めており、今、大きなプロジェクトを任されて苦戦しているという。
「先輩たちの期待に応えられるか不安で…」と鈴木は言った。
高田は自分の若い頃を思い出した。彼もまた、同じような不安を抱えていた。
「焦らなくていい」と高田は言った。「一歩ずつでいいんだ」
鈴木は少し安心したように微笑んだ。
この時、店の奥から女将が出てきた。
「あら、また来てくれたのね」と彼女は高田に言った。「何か食べる?」
「おでんをお願いします」
女将が奥へ戻ると、主人が黙って酒を注ぎ足してくれた。
「ありがとうございます」
時間が過ぎるにつれ、店内は少しずつ賑わってきた。サラリーマンのグループ、年配の夫婦、一人で飲む女性。様々な人々が「いさかや」に集まっていた。
おでんが運ばれてきた。湯気が立ち上り、優しい出汁の香りが広がる。高田は大根を一切れ取り、口に入れた。じんわりと染み込んだ出汁の味わいが体を温めた。
「美味しい」と高田は言った。
「でしょ」と女将は嬉しそうに答えた。「うちのおでんは二日仕込みなのよ」
高田と鈴木は、時折会話を交わしながら飲み続けた。話題は仕事から趣味、そして人生へと広がっていった。
「田中さんは、どんな仕事をしているんですか?」と鈴木が尋ねた。
「IT企業で営業をしています」と高田は答えた。「最近は新しいプロジェクトで忙しくて」
「大変そうですね」
「まあね。でも、こうして飲むと少し楽になる」
鈴木は頷いた。「僕もそう思います」
夜も更け、鈴木は「明日も仕事なので」と言って店を出た。高田は一人になり、静かに酒を飲み続けた。
カウンターの向こうで、主人は黙々とグラスを拭いている。その姿に、高田は不思議な安心感を覚えた。
「もう一杯どうですか?」と主人が尋ねた。
「お願いします」
主人が酒を注ぐ間、高田は思った。この「いさかや」には何か特別なものがある。人々の悩みを受け止め、少しの間でも心を休ませてくれる場所。彼はここに来るたびに、少しずつ強くなっているような気がした。
外は雨が降り始めていた。店内の温かな灯りが、より一層心地よく感じられた。高田はゆっくりと酒を飲み、雨の音に耳を傾けた。
明日のことは、また明日考えよう。今夜は、この静かな「いさかや」で心を休めることにした。
季節は移り、秋も深まっていた。高田は「いさかや」の常連となっていた。週に一度は必ず足を運び、カウンターで静かに酒を飲む。時には佐藤や鈴木と言葉を交わし、時には一人で思いにふける。
この日も、高田は仕事帰りに「いさかや」へと向かった。ドアを開けると、懐かしい香りと静かな空気が彼を迎えた。
「いらっしゃい」と主人は言った。いつもと変わらない淡々とした声だ。
「こんばんは」と高田は答え、いつもの席に腰を下ろした。
主人は黙って酒を注ぎ、お通しを置いた。「今日は里芋の煮っころがしだ」
高田が一口飲むと、体の芯から温まるような感覚があった。里芋も、ほっくりとして美味しい。
店内を見回すと、佐藤の姿があった。彼は高田に気づくと、軽く頷いた。
「久しぶりだな」と佐藤は言った。
「そうですね。お元気でしたか?」
「ああ、まあな」佐藤は酒を一口飲んだ。「お前はどうだ?あの問題は解決したのか?」
高田は少し考えてから答えた。「まだ途中です。でも、少しずつ前に進んでいます」
佐藤は満足そうに頷いた。「そうか。焦るな、時間がかかることもある」
二人は黙って酒を飲んだ。言葉を交わさなくても、不思議と気まずさはなかった。
この時、店の入り口が開き、一人の女性が入ってきた。高田は彼女を見て少し驚いた。以前、一人で黙々と飲んでいた女性だ。
彼女は高田を見ると、少し躊躇してから隣に座った。
「こんばんは」と彼女は言った。「以前も見かけましたよね」
「はい」と高田は答えた。「田中です」
「中村です」と彼女は自己紹介した。「この店、好きなんです」
「私もです」
女将が出てきて、中村に声をかけた。「いらっしゃい。久しぶりね」
「こんばんは」と中村は微笑んだ。「今日は何かおすすめありますか?」
「そうねぇ、今日は秋刀魚が新鮮よ」
「では、それをお願いします」
高田も秋刀魚を頼み、二人は軽く乾杯した。
「こういう古い居酒屋、最近は少なくなりましたよね」と中村は言った。
「そうですね。チェーン店が増えて…」
「でも、こういう場所にしかない魅力がありますよね」
高田は頷いた。確かに「いさかや」には、大きな居酒屋チェーンにはない温かさがあった。
秋刀魚が運ばれてきた。香ばしい匂いが漂う。中村は箸を取り、一切れを口に入れた。
「美味しい」と彼女は言った。「秋の味ですね」
高田も一切れ食べ、頷いた。「確かに。秋を感じます」
二人は会話を続けた。中村は出版社で編集の仕事をしているという。最近は新人作家の担当になり、忙しい日々を送っているとのことだった。
「良い作品に出会えることもあるけど、締め切りに追われることも多くて…」と中村は言った。
「大変そうですね」と高田は言った。「でも、やりがいはありそうです」
「そうですね。好きな仕事ですから」
会話が進むうちに、二人の距離は少しずつ縮まっていった。中村は時折笑顔を見せ、高田もリラックスして話をしていた。
佐藤は二人の様子を見て、にやりと笑った。「若いっていいな」
高田は少し恥ずかしくなり、咳払いをした。
夜も更け、佐藤は「そろそろ帰るか」と言って店を出た。高田と中村は二人きりになった。
「田中さんは、どうしてこの店に来るようになったんですか?」と中村は尋ねた。
高田は少し考えてから答えた。「最初は、何となく。でも、ここでお酒を飲んでいると、不思議と心が落ち着くんです」
中村は静かに頷いた。「分かります。私もそうです」
二人は再び黙って酒を飲んだ。カウンターの向こうで、主人は相変わらず無口に仕事をしている。時折、奥から女将の声が聞こえてくる。
「そろそろ帰りましょうか」と中村が言った。時計を見ると、もう11時を過ぎていた。
「そうですね」と高田は答えた。
二人は会計を済ませ、店を出た。外は冷え込んでいて、息が白く見えた。
「家はどちら方面ですか?」と高田は尋ねた。
「渋谷です」と中村は答えた。
「僕も渋谷方面です。よかったら、一緒に歩きましょうか」
中村は微笑んで頷いた。「はい、お願いします」
二人は静かな夜道を歩いた。話題は「いさかや」から、仕事、そして趣味へと広がっていった。
渋谷駅に着くと、中村は「今日はありがとうございました」と言った。
「こちらこそ」と高田は答えた。「また「いさかや」で会えたら嬉しいです」
中村は微笑んで頷いた。「はい、またぜひ」
別れる前、二人は連絡先を交換した。高田は家に帰る道すがら、心が軽くなっているのを感じた。
「いさかや」は彼の生活に、静かに、しかし確実に変化をもたらしていた。
冬の訪れを告げる寒い雨が降る夜、高田は「いさかや」のドアを開けた。店内は暖かく、心地よい。
「いらっしゃい」と主人は言った。「寒いな」
「こんばんは」と高田は答え、コートを脱いでハンガーにかけた。
いつもの席に座ると、主人は黙って燗酒を出してくれた。
「ありがとうございます」と高田は言った。「今日は寒いので、ちょうどいいです」
温かい酒が体を温める。高田はほっと息をついた。
この数ヶ月、彼の生活には少しずつ変化が訪れていた。仕事では新しいプロジェクトを任され、忙しくも充実した日々を送っている。そして、中村との関係も深まっていた。
「いさかや」で知り合って以来、二人は時々会うようになっていた。最初は「いさかや」で一緒に飲み、やがて映画を見に行ったり、休日に公園を散歩したりするようになった。
高田がぼんやりと考えていると、店の入り口が開き、中村が入ってきた。
「お待たせ」と彼女は言った。「仕事が長引いて」
「大丈夫、今来たところだよ」と高田は答えた。
中村は高田の隣に座り、女将が出てきて彼女に挨拶した。
「いらっしゃい。二人で来たの?」と女将は微笑んだ。
「はい」と中村は少し照れながら答えた。
女将は嬉しそうに二人を見た。「何か食べる?」
「おすすめは何ですか?」と高田は尋ねた。
「今日は鍋がいいわね。寒いから」
「では、鍋をお願いします」
女将が奥へ戻ると、主人は二人に酒を注いだ。
「乾杯」と高田は言った。
「乾杯」と中村も杯を上げた。
二人が話をしていると、店の入り口が再び開き、鈴木が入ってきた。彼は二人を見つけると、驚いた表情を見せた。
「田中さん、こんばんは」
「鈴木君、久しぶり」と高田は答えた。「彼女は中村さん。この店で知り合ったんだ」
「はじめまして」と鈴木は中村に挨拶した。
「こんばんは」と中村は微笑んだ。
「一緒にどう?」と高田は鈴木を誘った。
鈴木は少し躊躇したが、二人の隣に座った。
「最近どう?」と高田は鈴木に尋ねた。
「あのプロジェクト、なんとか形になりました」と鈴木は嬉しそうに答えた。「田中さんのアドバイスのおかげです」
「そう言ってもらえると嬉しいよ。でも、頑張ったのは鈴木君だ」
三人は話に花を咲かせた。やがて鍋が運ばれてきて、その香りに店内はより一層温かな雰囲気に包まれた。
「いただきます」と三人は言った。
鍋を囲みながら、彼らは「いさかや」で過ごした日々について話した。それぞれがこの店に初めて来た時のこと、ここで知り合ったこと、そしてこの店がもたらした変化について。
「不思議ですよね」と中村は言った。「この店に来なかったら、みんなと出会えなかった」
「そうだな」と高田は頷いた。「何かの縁かもしれない」
鈴木も同意した。「僕も、この店に感謝してます」
三人が話している間、主人は黙って彼らを見守っていた。時折、微かな笑みを浮かべることもあった。
夜も更け、店内のお客さんは徐々に減っていった。鈴木は「明日も早いので」と言って先に帰った。
高田と中村は二人きりになり、静かに酒を飲み続けた。
「この店に来るようになって、変わったことがあるよ」と高田は言った。
「何?」と中村は尋ねた。
「以前は、仕事のことばかり考えて、視野が狭くなっていた。でも今は…もっと広い世界が見えるようになった気がする」
中村は優しく微笑んだ。「私も似たような感じです。以前は常に締め切りに追われて、余裕がなかった。でも今は、少し立ち止まって考えることができるようになりました」
「いさかや」のおかげかな?」
「そうかもしれないですね。この店には、何か特別なものがありますから」
二人は「いさかや」を見回した。古い木の柱、かすれた看板、温かな灯り。この場所が、彼らにとって大切な場所になっていた。
「そろそろ閉店の時間だ」と主人が言った。
高田と中村は名残惜しそうに席を立った。会計を済ませ、コートを着る。
「また来るよ」と高田は主人に言った。
主人は黙って頷いた。しかし、その目には優しい光が宿っていた。
店を出ると、雨は上がっていた。冷たい空気が澄んで、星が見えている。
「送るよ」と高田は中村に言った。
「ありがとう」
二人は静かな夜道を歩いた。「いさかや」での温かな時間が、まだ心に残っている。
「次はいつ行く?」と中村は尋ねた。
「来週の金曜日はどう?」と高田は答えた。
「いいですね」
中村のアパートに着くと、二人は少し名残惜しそうに別れた。高田は家に帰る道すがら、「いさかや」のことを考えた。
あの店は単なる居酒屋ではない。人々が集まり、心を開き、少しずつ変わっていく場所。高田は「いさかや」に出会えたことを心から感謝していた。
そして、また来週。彼は「いさかや」のドアを開け、あの温かな空間に身を置くだろう。カウンターに座り、主人が注ぐ酒を飲み、女将の作る料理を味わう。そして、大切な人々と言葉を交わす。
「いさかや」は、これからも彼らの物語の一部であり続けるだろう。