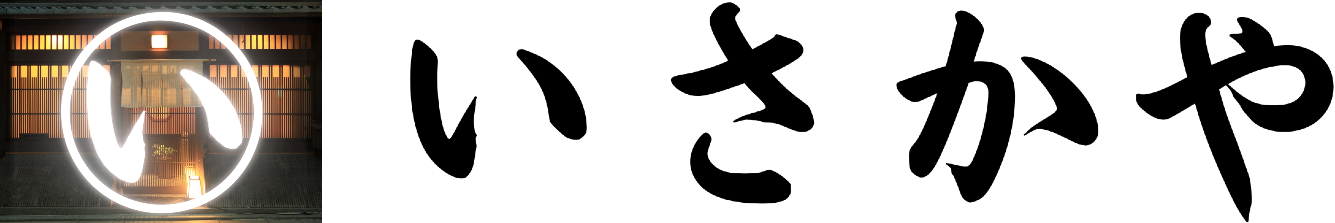※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
雨の匂いが鼻をつく六月の夕暮れ、私は池袋西口の雑踏をかき分けて歩いていた。駅を出てすぐの大通りは、帰宅を急ぐ会社員と買い物客で溢れかえっている。この雑多な人の流れこそが池袋の魅力であり、私がこの街の居酒屋を愛してやまない理由だ。
「いさかや」と名乗る私の仕事は、その名の通り居酒屋を巡り、その魅力を文章に込めること。今夜は西口のロマンス通りから少し入った路地裏にある、ある隠れ家的な店を目指していた。
トキワ通りを抜け、少し怪しげな雰囲気漂う細い路地を入る。昭和の香りが色濃く残るこの一帯は、再開発の波に飲み込まれながらも、頑なに昔の姿を残している。サンシャイン60のネオンが遠くに見えるのが、なんとも不思議な対比だ。
「あった、ここか」
看板もなく、ただ「一献」と書かれた赤提灯が揺れる木戸の前に立つ。引き戸を開けると、カウンター9席のみの小さな店内が現れた。
「いらっしゃい」
振り返った店主は、70を過ぎたであろう老人だった。白髪を後ろでまとめ、手には出刃包丁を握っている。まな板の上では、まだ動いている車海老が跳ねていた。
「初めてなのにようこそ。どうして知ったかね、ここは」
言われて気づいたが、店内には地元の常連らしき客ばかり。観光客や若者の姿は見当たらない。私は名刺を差し出した。
「いさかやと申します。居酒屋の記事を書いているものですが」
店主はちらりと名刺を見ると、にっこりと笑った。
「名前まで居酒屋とはね。縁だろう、座りな」
カウンターの一番端の席に案内される。この狭いカウンターが生み出す一体感は、池袋西口の老舗居酒屋ならではの特徴だ。となりに座る初老のサラリーマンは、もう赤ら顔になっている。
「マスター、いつものを」
言うなり、店主の手元からは絶妙な厚さに切られた刺身が出てくる。生きたまま捌かれた車海老は、皿の上でまだ痙攣していた。
「これが噂の『活け造り』ですか」と私。
「ああ、ウチは戦後からずっとやってる仕入れルートがあってね。市場に出回る前の最高の食材が手に入るんだ」
店主は誇らしげに言った。メニューを見ると、大衆価格とは思えない高級食材の数々。あん肝、まぐろ刺し、煮込み—いずれも市場相場の半額ほど。これが池袋の飲み屋の底力か。
「一献」の名物は、牛の煮込みだという。大きな土鍋から香り立つ湯気に誘われて、一杯目のビールを頼む。
「ビール大瓶、ね」
出てきたビールは520円と、駅前の居酒屋としては破格の安さ。昭和時代から価格据え置きなのだという。
少し観察していると、客の層が実に多様なことに気づく。サラリーマン、学生、外国人ツーリスト、地元のおばちゃん、若いホステス。池袋という街の縮図のような客層だ。
「最近は外国人のお客さんも増えたね」と店主。
「ネットで『本物の東京の居酒屋体験』って紹介されてるらしくてね。言葉は通じなくても、酒と肴があれば会話になるよ」
そう言って、店主は外国人客に向かって流暢な中国語で話しかけた。
「昔は中華料理屋だったんです」と耳打ちしてくれる。「70年代に居酒屋に転向したんだけど、中国の友人たちとの縁は大事にしてるよ」
時が経つにつれ、店内はさらに賑やかになっていく。隣のサラリーマンと、私は自然と会話を始めていた。
「池袋に30年住んでるけど、この店は40年変わらないよ」
彼は言う。「あの再開発の嵐の中でもな。マンモスプールがなくなり、西武百貨店も変わった。だけどここは、昭和の味を守ってる」
酒が進むにつれ、隣のサラリーマン・田中さんは思わぬ話を聞かせてくれた。彼は実は、かつてこの周辺一帯の再開発プロジェクトに関わっていたという。
「ここ、『一献』だけは触れられなかったんだ」
不思議に思って理由を尋ねると、田中さんはさらに声を潜めた。
「ここの地下には、戦時中の防空壕が続いているんだよ。再開発で掘り返したら、色々と出てくるものがある。闇市時代の名残というか…」
私の背筋に冷たいものが走った。
その時、店の奥から不思議な女性が現れた。店主の娘だろうか、年は40代半ばといったところだが、凛とした佇まいの美しい女性だ。
「お父さん、もう休みなさい」
その声は、まるで氷のように冷たかった。客たちが一瞬静まり返る。しかし店主は慣れた様子で笑う。
「あぁ、環が出てきたよ。皆さん、私の娘です」
環と呼ばれた女性は、無言で店主の包丁を受け取ると、さっと手際よく刺身を切り始めた。その包丁さばきは、まるで舞を見ているようだ。
「環は元は有名な料亭で修行していたんだ」と店主。「池袋に戻ってきたのは3年前。店を継いでもらおうと思ってね」
刺身が私の前に置かれる。透き通るように美しい鯛の薄造り。一口食べると、これまで味わったことのない旨みが口いっぱいに広がった。
「これは…普通の鯛ではない」
環は静かに頷いた。「ウチの鯛は、市場を通さず漁師から直接買い付けている特別なものです。父の代からの付き合いです」
そして環は、この店でしか味わえない特別な「池袋の食材調達ルート」について語り始めた。戦後の闇市時代、食料難の中で培われた独自の仕入れルートが、今もひっそりと生きているという。
「池袋は表向きは華やかでも、裏では昭和の記憶が生きている街なんです」
環の語る池袋の居酒屋史に、私はすっかり酔いしれていた。
夜も更け、店内はさらに熱気を帯びる。いつの間にか、環と私だけの会話になっていた。彼女は葛藤の末にこの店に戻ってきたという。一流料亭での腕を池袋の大衆居酒屋で振るうのは、最初は抵抗があったそうだ。
「でも今は、この街の記憶を守るのが私の使命だと思っています」と環。「再開発で街は変わっても、食の記憶だけは守りたくて」
最後に出てきたのは、店の秘伝という「水炊き鍋」だった。8時間かけて炊いたという鶏スープは白濁し、ほのかな柚子の香りが立つ。私は迷わず写真を撮り、メモを取った。
この味は、間違いなく記事の目玉になる。池袋の居酒屋が持つ二面性—表の華やかさと裏の深み。それを体現するような一杯だった。
夜が明けそうな頃、私は「一献」を後にした。
「また来てくださいね」
環の言葉が、霧雨の降る路地裏に響く。翌朝、私はこの体験を記事にすべくパソコンに向かった。しかし不思議なことに、写真には「一献」の内装は写っているのに、環の姿だけは霞んでいた。そして「水炊き鍋」の写真も、ぼんやりとしか写っていない。
慌てて田中さんから聞いた店の詳細を調べてみる。すると驚くべきことが分かった—「一献」の店主の娘・環は、10年前に亡くなっていたのだ。
私は恐る恐る再び訪れた「一献」に、環の姿はなかった。だが店主は私を見るなり、
「おや、環とはうまく話せたかい?」
と自然に尋ねてきた。私が写真のことを告げると、店主は深くため息をついた。
「環は写真に写らないんだよ。だから料理の写真も霞むんだ。彼女の魂が宿った料理はね…」
タクシーで帰りながら、私は考えた。池袋の居酒屋には、人々の記憶と魂が宿っている。それは単なる飲食店ではなく、この街の歴史そのものなのだ。あの夜、「一献」で味わったのは単なる食事ではなく、池袋という街の記憶の断片だったのかもしれない。
そしてこの記事が、彼女が守ろうとした「池袋の食の記憶」の一助になればと思いながら、私はタイピングを続けた。池袋の路地裏に咲く、一献の花の物語を。