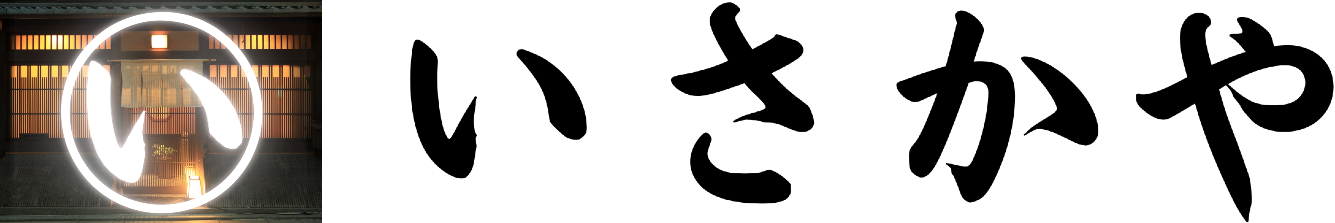梅雨の晴れ間、湿った空気が肌にまとわりつく六月の夕暮れ。仕事を終えた私は、古びた木造アーケードの下を歩いていた。昭和の香りが残る商店街は、かつての賑わいを失いつつも、しぶとく生き残る店々が点在していた。
「いさかや」という筆名で居酒屋評を書き始めて七年目。本名を明かさないのは、素直な感想を書くためだ。顔を知られれば、サービスが良くなるかもしれないが、それでは一般客が体験するものとは違ってしまう。
雨上がりの石畳が、夕暮れの光を反射して妙に美しい。ふと見上げると、半世紀は経っていそうな二階建ての木造建築の軒下に、「酒処 たまゆら」という提灯が揺れていた。赤く染まった空を背景に、その姿はどこか寂しげだ。
この店のことは聞いたことがある。地元の古老たちが通う隠れ家的な存在で、観光客向けのガイドブックには決して載らない場所だ。いわゆる「常連さんの店」。そういう場所に突然訪れる私のような者は、往々にして歓迎されない。
しかし、私の仕事は「本当の居酒屋」を探すこと。看板に偽りのない、素のままの飲み屋を見つけ出し、言葉にすること。そして、消えゆく昭和の酒文化を記録に残すことだ。
階段を上り、古びた引き戸を開ける。
「いらっしゃい」
低く、しかし温かみのある声が響いた。カウンターの内側に立つのは、七十を超えた老婦人。白髪を後ろでまとめ、藍染めの前掛けをしている。店内には既に三人の客がいた。全員が年配の男性で、私の入店に一瞬視線を向けたものの、すぐに各々の会話に戻った。
「お一人様?」
老婦人―おそらく女将―が尋ねる。私はうなずき、カウンターの端に座った。
「お冷やでよろしいですか?」
「はい、お願いします」
店内を見回す。カウンターは八席ほど、壁際には四人がけのテーブルが二つ。天井は低く、梁が露出している。壁には古びた暦や、黄ばんだ家族写真が飾られていた。どこか懐かしさを感じる空間だ。
「何にします?」
「とりあえずビールを」
女将はこくりとうなずき、グラスを取り出した。ジョッキではなく、薄手の硝子のグラス。それだけで、この店がどういう場所かがわかる。
「お通しは何がいい? 今日は冷奴、きゅうりの漬物、イカの塩辛があるよ」
「冷奴でお願いします」
女将は小さな冷蔵庫から豆腐を取り出し、丁寧に切り分けた。動作に無駄がない。長年の経験が生み出す所作の美しさだ。
「初めて来たかい?」
注がれたビールを一口飲んだところで、女将が話しかけてきた。シンプルな質問だが、常連以外お断りという店もある中で、これはある種の歓迎の言葉だ。
「はい。通りがかりで、提灯を見て気になって」
「そう。最近は若い人も来ないからね」
女将は冷奴を出しながら言った。刻みネギ、おろし生姜、鰹節がわずかに乗っている。派手さはないが、手抜きもない。
「この店、何年くらいやってるんですか?」
「うちかい? 私が継いで四十年。その前は姑が三十年ほどやっていたから、この場所で七十年になるね」
七十年。私自身の人生よりも長い。この店がどれだけの人の物語を見てきたのか、想像もつかない。
「すごいですね。変わらず続けるのは大変でしょう」
女将は少し笑った。しわの間から温かい目が覗く。
「変わらないものなんてないよ。この街も、お客さんも、私も、みんな変わってる。でも、酒を飲んで語り合う人の姿は、昔も今も同じかもしれないね」
その言葉に胸が詰まった。居酒屋という場所の本質を、この女将は知っている。私はもう一口ビールを飲み、少し勇気を出した。
「実は私、居酒屋について書く仕事をしています。『いさかや』というペンネームで」
女将は少し驚いたような顔をした後、ゆっくりとうなずいた。
「そう。でも、うちみたいな古い店を書いても、若い人は来ないだろうね」
「いいえ、そんなことはないと思います。形は変わっても、人と人が繋がる場所としての居酒屋は、きっとこれからも必要とされるはずです」
女将は何も言わなかったが、少しだけ嬉しそうな表情を見せた。
「何か食べる? メニューはないけど、今日は鯵の刺身と、鶏の唐揚げ、それから茄子の煮びたしがあるよ」
「全部お願いします」
女将は黙々と料理を作り始めた。包丁の音、油の跳ねる音、それらが心地よく響く。
カウンター越しに見える調理場で女将が動く姿を見ながら、私は思った。この店のことを記事にしたら、どう書こうか。派手さはないが、長年培われた確かな味と、ほどよい距離感を持った接客。そして何より、ここにしかない時間の流れがある。
料理が並び、酒が進む。女将との会話も徐々に増えていった。息子さんが東京で働いていること、昔はこの通りにも多くの飲み屋があったこと、そして最近は週に三日だけ店を開けていることなど。
「ねえ、あんた。うちのこと書くなら、あまり大げさに書かないでおくれよ」
最後のお酒を飲み終えた頃、女将がそう言った。
「ただの古い飲み屋だから。特別なものなんてないからね」
私は笑って答えた。
「でも、だからこそ特別なんです」
店を出る頃には、雨が上がり、星が見えていた。来た時より少し軽い足取りで、私は商店街を抜けていった。明日、この店のことを書こう。しかし、この場所で感じた温かさを、どれだけ言葉にできるだろうか。
居酒屋という場所が持つ魔法は、そこで交わされる言葉や料理だけではなく、共有される時間の中にこそある―そう思いながら、私は夜の街へと消えていった。