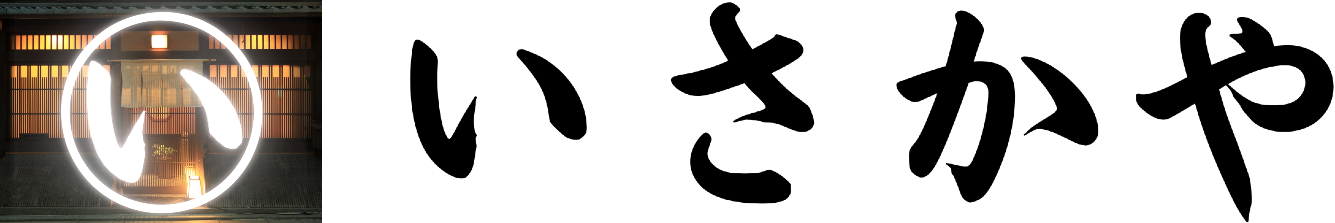※この物語は実際の取材をもとに、一部フィクションを交えて創作したものです。
雷門から伸びる仲見世通りを抜け、浅草寺の大提灯を見上げた後、人混みから少し外れた路地に入ると、そこはもう別世界だった。観光客でごった返す表通りと違い、地元の人々の生活が息づく場所。私、いさかやは居酒屋ライターとして、浅草の居酒屋文化を取材するため、この街を訪れていた。
神楽坂での取材を終えてから一週間。今日の目的地は、創業70年を誇る老舗居酒屋「雷門屋」だった。看板もなく、ただ「のれん」だけが下がる質素な外観。観光ガイドには載っていない、地元の人だけが知る隠れ家的な店である。
「いらっしゃい」
暖簾をくぐると、柔らかな明かりと優しい声が迎えてくれた。70代と思われる主人が、カウンターの中から笑顔を向けている。店内は昭和の香りがする古い造りで、カウンター8席とテーブル3つというこじんまりとした空間。既に数人の常連客らしき人々が、思い思いに酒を酌み交わしていた。
「初めまして。いさかやと申します。取材のお願いをしていた者です」
事前に電話で取材の許可を得ていたのだ。主人は大きく頷くと、カウンターの一番端の席を勧めてくれた。
「山田だ。よく来てくれたね。浅草の居酒屋について書くんだろう?」
山田さんは、昭和20年代後半から両親と共にこの店を営んできたという。戦後の混乱期から高度経済成長期、バブル崩壊、そして現在のインバウンド観光ブームまで、浅草の変遷を見守ってきた生き証人だった。
「お通しですよ」
出されたのは、シンプルな枝豆とたくあんだった。しかし、その枝豆は程よい塩加減で、ビールとの相性が抜群だ。
「浅草で長く商売を続けるコツは何ですか?」
この質問に、山田さんは少し考え込んだ。
「変わらないことと、変わることの両立かな。浅草の居酒屋は観光客相手に目新しいことをする店もあれば、地元の常連のために変わらない味を守る店もある。うちは後者だね」
彼の言葉には重みがあった。70年という歳月は、決して平坦な道のりではなかっただろう。
「おすすめの一品は?」
「今日なら『どぜう』だね。浅草といえばどぜうだ。昔ながらの調理法で作るから、ちょっと時間がかかるけど」
「どぜう」とは、どじょうを柳川鍋のように調理した江戸時代からの郷土料理だ。私はもちろん注文した。
待っている間、山田さんは浅草の歴史を語ってくれた。浅草寺の門前町として栄えた江戸時代、花街として賑わった明治・大正時代、そして戦災で焼け野原になりながらも復興を遂げた戦後の浅草。
「浅草の居酒屋文化は、こうした歴史の中で育まれてきたんだよ。どの時代も、人々の憩いの場として居酒屋は欠かせなかった」
隣に座っていた年配の男性が、話に加わってきた。
「私は50年来の常連だよ。山田のお父さんの代からの付き合いでね」
佐藤さんという彼は、近くで印刷業を営んでいるという。浅草のことを知りたければ彼に聞けと山田さんは言う。
「浅草の面白いところは何ですか?」と尋ねると、佐藤さんは目を細めた。
「何と言っても人情だね。浅草の居酒屋は、料理や酒も大事だけど、人と人との繋がりが最も大切にされている。だから古い店が多いんだ」
そう言って彼は、店内の様々な人を紹介してくれた。向かいのテーブルに座る白髪の女性は元芸者だという。カウンターの中ほどで一人酒を楽しむ男性は落語家の卵。そして奥のテーブルで話し込む若い二人組は、近くで浅草をテーマにした本を出版する編集者たち。
「浅草は小さな世界だよ。みんな顔見知りでね。浅草の居酒屋は、そうした地域コミュニティの核になっている」
そんな話をしている間に、待ちに待った「どぜう」が運ばれてきた。小さな土鍋の中で、どじょうがねぎやごぼうと共に煮込まれている。一口食べると、優しい出汁の味わいと、ほのかな山椒の香りが口の中に広がった。
「これは…絶品です」
山田さんはにこりと笑った。
「秘密は三種類の出汁を使うことだよ。昆布、鰹節、そして…ここからが企業秘密」
彼は茶目っ気たっぷりに目を細めた。その笑顔には、職人としての誇りと、客を楽しませる余裕が感じられた。
店内の会話は次第に賑やかになっていった。ビジネスマン、地元の商店主、観光関連の仕事をする人々、そして数人の外国人観光客も。様々な人々が、この小さな空間で時間を共有している。
「最近は外国人のお客さんも増えたでしょう?」
「ああ、浅草の居酒屋は外国人観光客にも人気なんだよ。特に本物の日本を体験したい人たちが来る。彼らは派手な観光地よりも、こういう地元の人が通う店を好むんだ」
そう言って山田さんは、入口近くの壁を指さした。そこには世界各国から送られてきたという絵葉書が貼られていた。帰国後も、この店の思い出を大切にしている人々からのメッセージだ。
「言葉は通じなくても、美味しい食事と酒があれば仲良くなれるものさ」
その言葉通り、奥のテーブルでは日本人客と外国人観光客が、片言の英語と日本語を交えながら盃を交わしていた。言葉の壁を超えた交流が、そこにはあった。
夜が更けるにつれ、店内の雰囲気はさらに和やかになっていった。誰かが小さな三味線を取り出し、古い江戸小唄を奏で始めた。周りの客も自然と手拍子を打ち、中には小声で歌う人もいる。
「これは浅草の夜の風物詩だよ。浅草の居酒屋では、こうして即興の演芸が始まることもあるんだ」
佐藤さんはそう説明してくれた。芸能の街・浅草ならではの光景だろう。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、気がつけば閉店時間が近づいていた。最後に残ったのは、私と佐藤さん、そして数人の常連客だけだった。
「山田さん、素晴らしい夜をありがとうございました」
「こちらこそ。また来てくれよ」
握手を交わした山田さんの手には、長年の商売で培われた温もりがあった。
「明日、もし時間があれば昼過ぎに来なさい。浅草の裏路地を案内するよ」
佐藤さんのその申し出に、私は喜んで承諾した。
翌日、約束通り「雷門屋」を訪れると、佐藤さんは既に待っていた。日中の「雷門屋」は居酒屋ではなく、かつての定食屋として営業しているという。ランチを共にした後、私たちは浅草の裏路地へと歩き出した。
「観光客があまり行かない、地元の人たちの浅草を見せてあげよう」
佐藤さんの案内で訪れたのは、細い路地に連なる昭和の香りがする商店街、職人たちが今も伝統工芸を守る工房街、そして夕方から灯りが灯り始める小さな飲み屋街だった。
「浅草の居酒屋は、こうした裏路地にこそ名店が潜んでいるんだよ」
彼の案内で、私たちは何軒かの小さな店を覗いた。どの店も外観は質素だが、中に入ると驚くほど洗練された料理や、希少な地酒を提供している。しかも、観光地価格ではなく、良心的な値段設定だ。
「観光客向けの店は表通りに任せて、浅草の居酒屋の本当の姿は、こうした路地裏にあるんだ」
路地裏散策の最後に、佐藤さんは不思議な場所に私を連れて行った。それは小さな神社だった。鳥居をくぐると、わずか畳二畳ほどの境内に、小さな祠が鎮座している。
「これは『酒神社』。江戸時代から酒に携わる人々の守り神として祀られてきたんだ」
神社の傍らには、古い石碑があり、「大正十二年 関東大震災にても無事」と刻まれていた。
「この神社だけは、不思議と災害を免れてきたんだ。浅草の居酒屋の人々は、今でも商売繁盛と無病息災を祈願して参拝に来るよ」
佐藤さんは懐から小さな徳利を取り出し、祠の前に供えた。
「新しい酒が入荷するたびに、最初の一滴をここに奉納するんだ」
その姿には、現代に生きながらも古き良き伝統を大切にする浅草の人々の精神が表れていた。
「ところで、この神社には不思議な言い伝えがあるんだ」
佐藤さんの声が少し低くなった。
「大晦日の夜、この神社に一人で参拝し、心の底から願い事をすると、その年の酒運が開けるという。しかし、欲深い願いをすると逆に酒が飲めなくなる…」
彼の語る伝説は、本当かどうか判断しかねるものだったが、浅草という街の神秘性を感じさせるものだった。
「本当の話かどうかは分からないよ。でも、浅草の居酒屋文化には、こうした言い伝えや伝説が溶け込んでいる。それも魅力の一つさ」
日が傾きはじめ、浅草の街には夕暮れの影が落ち始めていた。佐藤さんとの別れ際、彼は一枚の古い写真を私に手渡した。
「昭和30年代の浅草だよ。今とは随分違うだろう?」
その写真には、今よりもずっと下町風情が色濃い浅草の風景が映し出されていた。路面電車が走り、人々は着物姿。そして通りには小さな屋台や露店が立ち並んでいる。
「外見は変わっても、人の温かさは変わらないんだ。それが浅草のいいところさ」
佐藤さんの言葉には、郷土への深い愛情が込められていた。
「雷門屋」での取材を終えた私は、その後も数日間、浅草の様々な居酒屋を訪れた。観光客向けの大箱から、地元の人だけが知る隠れ家まで。どの店にも、それぞれの個性と魅力があった。
しかし、どの店を訪れても、共通して感じたのは「人情」という言葉だった。浅草の居酒屋は、単なる飲食店ではなく、人と人とが心を通わせる場所だった。初めて訪れた客にも分け隔てなく接し、常連客とは家族のように親しく交流する。そこには、下町特有の温かさがあった。
最終日、私は再び「雷門屋」を訪れた。今日はお礼を言うためだ。店に入ると、山田さんは昨日と同じ場所でカウンターを拭いていた。
「ああ、いさかやさん。どうだった?浅草の居酒屋巡りは」
「素晴らしかったです。特に佐藤さんに案内していただいた裏路地の店々は、忘れられない体験になりました」
山田さんは満足げに頷いた。
「浅草は表と裏、両方見ないと本当の姿は分からないからね」
別れ際、山田さんは古い木の升を私に手渡した。
「うちの店のロゴ入りだ。記念に持っていきなさい」
木の香りがする手触りの良い升。それは浅草での思い出と共に、私の大切な宝物となるだろう。
「次はどこを取材するんだい?」
「月島を考えています。もんじゃ焼きの店を中心に」
「ああ、あそこも良いところだ。浅草とはまた違った下町の魅力があるよ」
山田さんの言葉に力をもらい、私は次なる取材地へと思いを馳せた。
浅草を後にする夕暮れ時、雷門の大提灯に最後の別れを告げながら、私は思った。浅草の居酒屋文化は、この街の歴史と共に歩み、人々の記憶を繋いできた。そして、これからも変わりゆく時代の中で、新たな物語を紡いでいくのだろう。
路地裏から聞こえてくる三味線の音色と共に、私の浅草取材は幕を閉じた。しかし、この街で出会った人々との縁は、これからも続いていくに違いない。
次回は、月島の居酒屋を訪ねる予定だ。下町ののれんを潜るたび、新たな物語が待っている。それを記録するのが、私、いさかやの仕事なのだから。